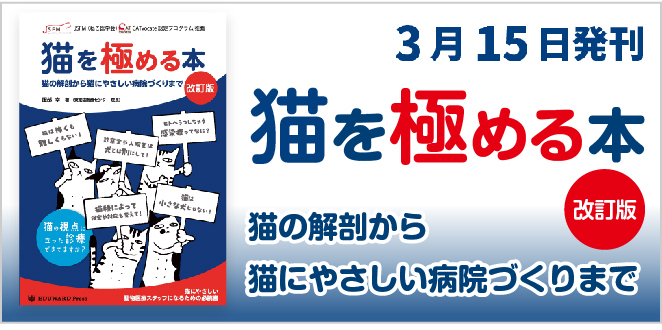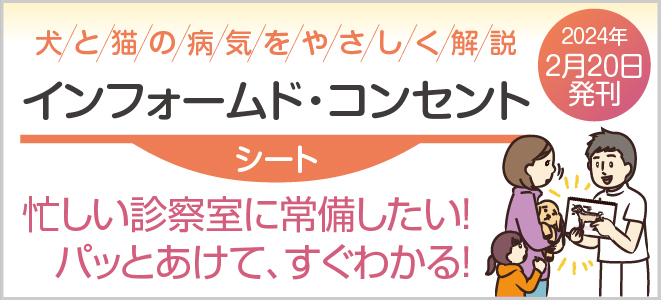人と犬猫のためのイベント「sippo EXPO」を初開催
保護犬猫譲渡会&人気ブロガー・まめきちまめこコラボ企画も!
10月25~27日@東京ビッグサイト

ニュース概要
株式会社朝日新聞社(代表取締役社長:角田克)の犬猫情報サイト「sippo」は、保護犬猫の譲渡会や、新しい家族が見つかった元保護犬猫の「今」を紹介する写真展などさまざまな企画を盛り込んだ「sippo EXPO」を10月25~27日、東京・有明の東京ビッグサイトで初開催します。同期間に開かれる「GOOD LIFE フェア2024」(朝日新聞社主催)の一環。譲渡会は事前予約制で参加無料。協賛ブースもあります。
■sippoサイト ■GOOD LIFE フェア2024
https://sippo.asahi.com/ https://goodlife-fair.jp/
sippoサイトは「犬や猫ともっと幸せに」をコンセプトに2017年にスタート。捨てられた犬猫を殺処分から救う取り組みに力を入れ、企業や動物保護団体と連携し、東京や大阪で譲渡会を開催してきました。譲渡会に参加した方からは「保護犬猫の支援活動を知る機会になった」などの声が寄せられています。
「sippo EXPO」の譲渡会には、動物保護団体の皆さまのご協力で、のべ約60匹の犬と猫が参加する予定です。幸せになった元保護犬猫の姿を飼い主さんのメッセージと共大に型モニターで紹介するデジタル写真展「みんなイヌみんなネコ」sippo EXPO編や、人気ブロガー・まめきちまめこさんとのコラボ企画(スタンプラリー/トークショー)も予定しています。
https://sippo.asahi.com/article/15450193
10月25~27日の各日とも、午前は猫、午後は犬の譲渡会を開きます。保護犬猫をご家庭に迎え入れたい方のご応募をお待ちしています。定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
■参加いただく保護団体の皆さま
10月25日(金)
午前の部・保護猫譲渡会:保護猫カフェ「ねこかつ」
午後の部・保護犬譲渡会:認定NPO法人アニマルレフュージ関西-東京ARK-、NPO法人わんにゃんレスキューOHANA
10月26日(土)
午前の部・保護猫譲渡会:一般社団法人おーあみ避難所
午後の部・保護犬譲渡会:一般社団法人おーあみ避難所
10月27日(日)
午前の部・保護猫譲渡会:一般社団法人東京都人と動物のきずな福祉協会、保護猫カフェ「ねこかつ」
午後の部・保護犬譲渡会:いぬ助け
■犬猫譲渡会「sippo EXPO」のお申し込みはこちら(無料)
10月25日 https://sippoexpo-jyotokai1025.peatix.com
10月26日 https://sippoexpo-jyotokai1026.peatix.com
10月27日 https://sippoexpo-jyotokai1027.peatix.com
*「GOOD LIFE フェア2024」は、完全登録制のイベントです(前売り1,000円、当日1,300円、招待者無料)。譲渡会を予約いただいた方には、入場無料になる招待コードをお送りします。