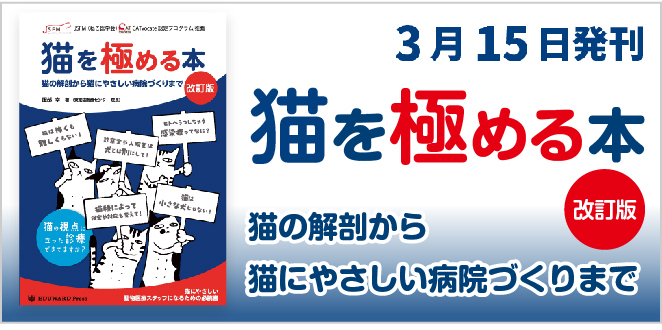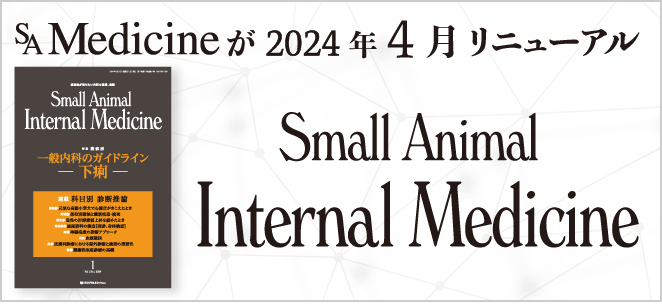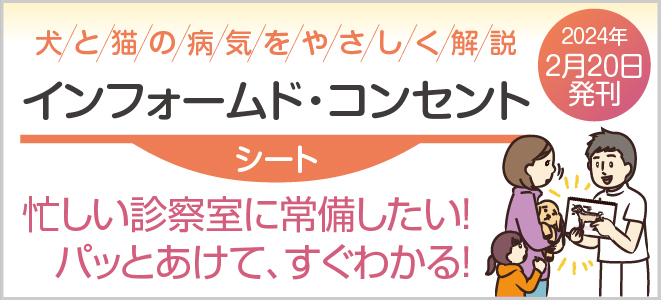各分野のトップランナーが、どのように学んできたのか。
そして、どのように学びを臨床に活かしているのか。
「明日の獣医療を創る」は、すべての臨床獣医師に捧げるインタビューシリーズ。
第7回は藤井仁美先生です。

みんな「いいコ」であることの驚き
―藤井先生が動物の行動診療に携わるようになったきっかけを教えてください。
夫の海外赴任にあわせて移住したことが、行動診療との出会いといえます。獣医師になったばかりの頃は一般的な動物病院で働いていましたが、まずは2年ほどシンガポールへ、その後はロンドンへとわたり、育児の傍らで動物病院の診察を見学したり、処置手伝いなどのボランティアに携わりました。
ロンドンの動物病院では、診察中の犬たちを飼い主が保定できるほど、みんな「いいコ」であることに気付き、とても驚きました。私が海外へわたる前の日本(1995年頃)は、現在ほど動物のしつけが盛んではない時代でしたので、犬に口輪をはめたり、動物看護師が無理な保定をするなど、苦労しながら診察を行っていたような記憶があります。「どうしてこんなにお利口な態度で処置させてくれるのだろう?」「なぜ病院そのものを怖がらないのだろう?」「そもそも、何で飼い主が保定をしているの?」といった私の疑問に対して、院長や同僚からは「それは、パピーの教育も社会化もできているから」と、さも当たり前のように返されました。動物にはしつけやトレーニングが必要ということを飼い主が理解している、つまり文化として当たり前ということでした。
そういわれても、私にとっては当たり前のことではないのですから(笑)。これは面白いと感じて、しつけやトレーニングを学ぶようになりました。学んでいくと、すぐに“しつけやトレーニングを理解するためには動物行動学が必要”ということに気付き、動物行動学を習得しはじめました。そして、欧米で獣医行動診療が確立していった時代ということもあり、行動診療へと傾倒していきました。ちょうど日本でも、森 裕司先生や南 佳子先生・武内ゆかり先生らが獣医動物行動研究会を設立するなど、過渡期の時代でもありました。
―藤井先生は行動診療としつけ・トレーニングをどのように分けて考えていますか?

行動診療は「なぜこの動物が問題行動を起こすのか?」を明らかにして診断するものであり、獣医師はその診断に対してどのような治療プランがあるかを飼い主に提示しつつ、その方法を飼い主自身が実践することもサポートする…、そしてときに薬物を処方して治療を補助するというものです。一方、しつけ・トレーニングは、もともとは犬に作業や仕事をさせる際に、それを「犬に教えるためのもの」でした。
したがって、「しつけやトレーニングは、飼い主ではなくトレーナーの先生が動物にやり方を教えるもの」というイメージが、飼い主には強いようです。しかし、行動診療におけるしつけ・トレーニングとは、パピーの頃から適切に行うことによって問題行動を予防するためのものであり、さらに問題行動が起きてしまった際は、治療プランの中で犬(場合によっては猫)の行動を変える(変容する)ために行うプログラムとなります。したがって、この場合は飼い主にそのやり方を覚えてもらい、家で毎日実践していただかなくてはいけませんので、飼い主と動物の双方をみたうえでのカウンセリングが必要となります。つまり、“トレーニングの必要性を飼い主にも理解してもらう”ためのカウンセリングを行うのも、行動診療の中では非常に重要だということです。また、トレーニング以外の治療プランには、「環境や飼い主と動物との関係を改善」「飼い主の意識そのものを変えていく」といったことも含まれています。飼い主が動物を間違った形で擬人化することが原因となり、問題行動が起こっていることが多いからです。
もう一つ行動診療の重要な柱として、病気との鑑別もしくは病気との併発のケースを明らかにして、その双方の治療を同時に進めることがあげられます。病気自体が犬・猫を不安にさせますから、病気の治療を進めつつ、行動診療で不安を取り除くための環境改善や生活改善を、飼い主と一緒に考えて実践していただくということです。
SA Dermatology(2018年1月号)でも執筆しましたが、猫の場合、痒くて舐めてはいるものの、環境的なストレスが加わると、その痒みが増幅されて執拗に舐め続けることもあります。痒み自体を軽減する治療を行いつつ、環境的・社会的なストレスを軽減する総合的なアプローチが、行動診療の重要な目的の一つなのだと思っています。
―いま問題行動がみられる動物では、飼い主と動物自身、どちらがより高い要因をもっていると感じていますか?
昔は飼い主自身に問題があるケースがほとんどでしたが、近頃の飼い主はしつけや行動診療に高い関心をもっており、ある程度の知識を習得されている方も増えています。そのため、いま私ところに相談にくるケースでは、犬自身に問題があるケースが増えてきています。例えばてんかんの気質があったり、不安を感じやすい気質があったり、あとは飼い主と犬との環境があっていないといったどちらにも要因があるケースもあります。