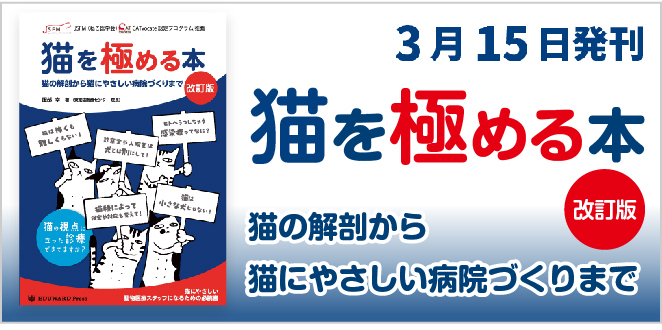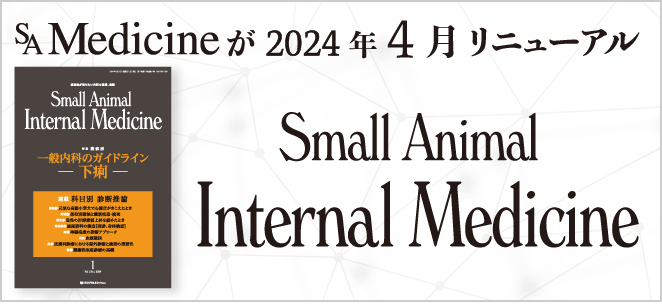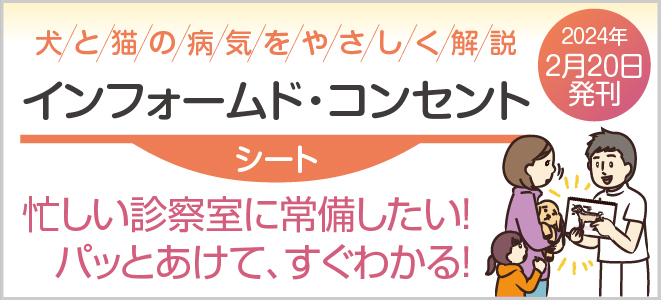各分野のトップランナーが、どのように学んできたのか。
そして、どのように学びを臨床に活かしているのか。
「明日の獣医療を創る」は、すべての臨床獣医師に捧げるインタビューシリーズ。
第4回は大隅尊史先生です。
※本インタビュー記事は、2017年7月に取材した記事を再編集したものです。

凄い世界をみせてくれる出会いを“面白い”と感じた
―大隅先生が皮膚科でキャリアを積もうと思われたきっかけはなんだったのでしょうか。
大学2年生の頃、ふとしたきっかけから都内の動物病院にて1ヵ月間研修をする機会がありました。その中でも記憶に残っているのが、重い皮膚疾患のために1カ月以上入院し、退院できないまま私の研修が終わってしまったラブラドール・レトリーバーの症例です。入院までしているのに皮膚疾患が治らないことにショックを受け、「治してあげたい」と強く思ったことが、皮膚科におけるキャリアのはじまりでした。
皮膚科は、診断をつけることがとても難しい分野です。X線検査で明確にわかる骨折や、検査数値だけで診断できる疾患ではありません。いろいろな要因を総合的に判断し、評価していくのが皮膚科という学問だと思います。私は、それがクイズやパズルを解いているような感覚に似ていると感じています。元々、私はロジックで物事を考えるのが好きで、問題をひとつずつ解いていくと全部クリアになる、みたいなことに楽しみを覚える性格です。そういった性格も相まって、学生のうちから皮膚科診療にチャレンジしてみたいと思っていました。
ただ、日本大学に通っていたときは、授業に少し物足りなさを感じ、真面目に授業を受けるタイプではありませんでしたね(笑)。ゼミに入って、そこで長谷川篤彦先生の指導を受けたことで、初めて「本気を出さないとヤバい」とスイッチが入りました。長谷川先生はロジックで物事を考える方で、知識もとても豊富です。指摘する点も的を射ています。圧倒的な存在で「この先生には敵わない」と思いながらも、「こんな考え方をすれば、今とは違う世界がみられるのか」と興奮したのを覚えています。
また、長谷川先生の勧めで卒業後に進んだ東京大学の内科で、先生方が容赦なきディスカッションを繰り広げていたことにも刺激を受けました。「学問の場では立場の上下がない」という、フラットな世界で育つことができたのは、私の強みになっていると思います。
―その後、一次診療そして二次診療の場に移られた理由は?
東京大学では、皮膚疾患の研究だけではなく一般診療も担当し、他科も一通り診ることができるようになりました。これも私の強みだと思います。というのも、皮膚疾患には内分泌疾患などの病気が関係することも多く、また外傷や腫瘍も関連することがあるため、“皮膚疾患を判断するベースとしての基礎知識”が身についたことで、皮膚疾患と他の病気との関連性がわかるようになり、一緒に治療もできるという自信もつきました。
しかし、約5年間務めた一次診療での皮膚疾患治療で、一定の結果を出せるようになったことで、「自分は皮膚科を全部診ることができる」と過信しはじめた時期もありました。ですが、さらに上を目指すため、アジア獣医皮膚科専門医のレジデントとして東京農工大学に籍を置いてから、「自分の知識なんてまだまだだ」と気づかされました。「私がわかっていることは、たったこれっぽっちしかない」、と。
入りたての頃は、指導医である西藤公司先生の方針にモヤモヤすることもありました。しかし、西藤先生の下で働きながら勉強していると、西藤先生は私がこれまでよしとしていたほんのわずかな可能性すらも考慮し、的確にポイントをつく診療をされていたことがわかるようになりました。西藤先生に目を開かされ、さらに自分の世界が広がったのだと思います。おそらく、この世界を突き詰めていくことが「世界水準の皮膚科医」へと続いていくのだと思います。
これは媚びているのではなく、指導者との出会いが自分を成長させてくれているという思いです。