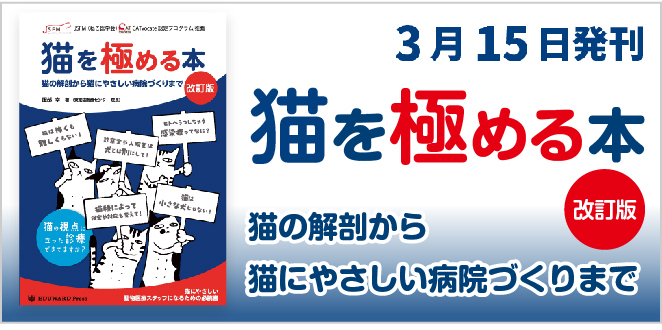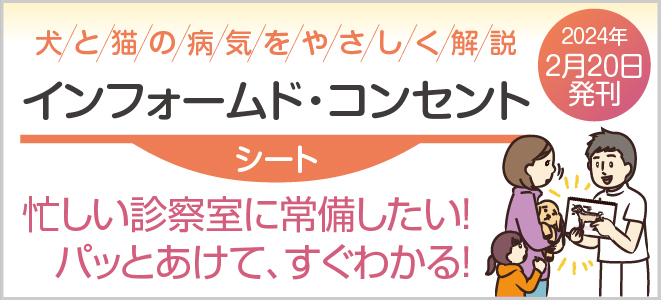<ポイント>
光を感知する役割を担う光受容タンパク質※1の不活性化において、最も重要な働きをするタンパク質の一つであるアレスチン※2を調査し、2種類のアレスチンを発見。
一つの細胞での光感知と色検出の働きは、2種類のアレスチンが光の強弱によって切り替わることで起きることを解明。

ニュース概要
<概要>
魚類など哺乳類以外の多くの脊椎動物は、目だけでなく、脳内の松果体※3という器官で光を感じたり色を検出したりすることが分かっています。
大阪公立大学大学院理学研究科の寺北明久教授、小柳光正教授、沈宝国博士(研究当時、大学院生)、和田清二博士(研究当時、特任助教)、東京大学理学系研究科の小澤岳昌教授らの研究グループは、ゼブラフィッシュの松果体において光を感知する光受容タンパク質のパラピノプシン1※4(PP1)を含む1種類の光受容細胞※5(PP1細胞)の色検出で、光受容タンパク質の不活性化に最も重要な働きをするタンパク質の一つであるアレスチンについて調査。その結果、2種類のアレスチン(Saga/bとArr3)の存在を明らかにしました。また、弱い光にはArr3が素早い不活性化に利用され、強い光にはSagbがゆっくりとした不活性化を担うことが分かりました。さらに、アレスチンのPP1への親和性は、Arr3がSagbよりも高いことが示唆されました。これらの結果から、光が弱い時は光の有無を感知し、光が強い時は色を検出するという、一つの細胞で二つの働きを担うには、2種類のアレスチンが光の強弱によって切り替わることで起きると判明しました。
今回の発見により、1細胞に複数種類あるアレスチンを刺激の強さに応じて使い分けている可能性も考えられ、アレスチンの機能解明に向けた重要な研究成果といえます。また、1種類の光受容タンパク質による色識別のメカニズムを解明したことは、パラピノプシンを用いて細胞を光の色で制御する技術の実現にも寄与するものと期待されます。
本研究結果は、2024年12月28日に国際学術誌「iScience」にオンライン掲載されました。
沈 宝国博士(現、温州医科大学博士研究員)より
この研究中、私は数々の失敗を経験し、またトラブルも多かったです。その一方で、PP1細胞に初めてArr3aを同定したときは、2日間興奮しっぱなしだったことを今でも鮮明に覚えています。とにかく、この研究は私にとても幸せをもたらし、そして自分を成長させてくれました。
<研究の背景>
ヒトの色覚(色の検出)は、目の網膜に存在する、赤、緑、青のそれぞれの色を感じる光受容タンパク質を1種類ずつ含む3種類の光受容細胞が担っています。一方、魚類や爬虫類など、哺乳類以外の脊椎動物の多くは、脳内に存在する松果体と呼ばれる器官で、光の有無だけでなく色を検出することが知られています。これまでに本研究グループは、硬骨魚類の松果体において、パラピノプシン1(PP1)と呼ばれる光受容タンパク質を含む1種類の光受容細胞(PP1細胞)が色検出を担っているという、目での色覚とは全く異なるしくみで色を検出していることを明らかにしました。具体的には、PP1が光を受けて情報を伝える状態(活性型)と暗状態(不活性状態)の二つの安定な状態の量比が、色の違い(光の波長分布の違い)により変化することで、色を検出するというものでした。
すなわち、不活性状態はUV/紫光に感受性があるので、UV/紫光の成分が多い光では、多くの不活性型が活性型へと光変換し、活性状態は緑色光を中心とする可視光に感受性があるので、緑色光などの可視光の成分が多い光のもとでは、活性型が不活性型へと変換し活性型量が減少します。このような「光平衡※6」を形成することにより、光の色の違いで活性型の量が決まり、色を感知するしくみです。
一般に目では、光を受けて生成した活性型は、直ちに不活性型にされ、光受容細胞の光応答がOFFになります。もし、この不活化が遅いと残像が残ることになるからです。一方、先行研究においてPP1細胞は、光が弱い時は視覚の細胞と類似して明暗応答をし、直ちに応答がOFFになりますが、色検出を行う比較的強い光のもとでは、活性型の量が光平衡の変化とともに時間をかけて変化することと関係して、ゆっくりとしたPP1の不活性化が必要であることを示唆していました。
しかし、その不活性化機構は未解明のままでした。

図1:魚類松果体のパラピノフシン(PP1)細胞における色検出光の色によりPP1の不活性型と活性型の比率が異なり、色(波長)が検出される。
<研究の内容>
本研究では、ゼブラフィッシュ松果体における色検出応答に関して、光受容タンパク質の不活性化において最も重要なタンパク質の一つであるアレスチンに着目。PP1細胞にあるアレスチンを組織科学的に調べたところ、2種類のアレスチン(Saga/bとArr3)の存在が明らかになりました。
次に、それぞれのアレスチン遺伝子の発現を低下させることにより、PP1発現細胞の光応答にどの程度の影響が生じるのかを、カルシウムイオン変化のライブイメージング※7により解析しました。その結果、Arr3は光が弱い時の素早い不活性化に利用され光強度が増すと、Arr3に代わりSagbが不活性化を担っていることを見出しました。また、培養細胞を使った実験から、アレスチンのPP1への親和性は、Arr3がSagbよりも高いことが示唆されました。これらの結果から、光が弱い時は明暗応答し、光が比較的強い時は色検出応答をするという1細胞2役の働きには、2種類のアレスチンが光の強さに依存して切り替わることが関与していると判明しました。

図2:パラピノプシン(PP1)の活性型の不活性化における光強度に応じた2種類のアレスチン(Arr3、Sagb)のスイッチング
<期待される効果・今後の展開>
これまでに、複数種類のアレスチンが一つの細胞に存在していることは知られており、ゼブラフィッシュは7種類のアレスチン遺伝子を持っています。今回の発見から刺激の強さに応じて使い分けている可能性も考えられ、アレスチンの機能解明に向けた重要な研究成果といえます。また、1種類の光受容タンパク質による色識別のメカニズムを解明したことは、パラピノプシンを用いて細胞を光の色で制御する光遺伝学※8の実現にも寄与するものと期待されます。
<資金情報>
本研究は、日本学術振興会科研費基盤研究(S)JP15H05777、基盤研究(B)JP23H02516、JP18H02482、JP22H02663、若手研究JP18K14751、基盤研究(C)JP21K06265、JP20K15844、基盤研究(A)JP22H00322、科学技術振興機構(JST)CREST JPMJCR1753の支援を受けて実施しました。
<用語解説>
※1 光受容タンパク質:
オプシンとも呼ばれ、視覚の光受容タンパク質である視物質と似たタンパク質である。光をキャッチし、細胞内において情報伝達を担う別のタンパク質(Gタンパク質)に光の情報を引き継ぐ。Gタンパク質に情報伝達する受容体ファミリーであるGタンパク質共役型受容体(GPCR)の一種。
※2アレスチン:
光受容タンパク質やGPCRに結合し、Gタンパク質への情報伝達を阻害するタンパク質(※1参照)。アレスチンによる情報伝達の停止は、光応答の時間分解能や感度調節の点から重要であり、視覚においてアレスチンの働きが十分でないと残像やまぶしさが生じると考えられる。
※3松果体:
脳内のメラトニンの内分泌器官。哺乳類を除く多くの脊椎動物の松果体やその関連器官は光を受容することから第3の目とも呼ばれる。爬虫類、両生類、硬骨魚類、円口類の松果体関連器官は、光の有無・強弱だけでなく、UVと可視光の比率など、「色」の違いも検出する。
※4パラピノプシン1:
哺乳類と鳥類を除く多くの脊椎動物の松果体関連器官に特異的に存在するUV感受性の光受容タンパク質であるパラピノプシンの一種。硬骨魚類は、パラピノプシン1と2の2種類のパラピノプシンを持つ。
※5光受容細胞:
光受容タンパク質を含み、光を受容することに特化した細胞。
※6光平衡:
光受容タンパク質オプシンは、暗中で光を受容していない暗状態ではOFF(不活性)型であり、光受容すると光産物に変化しON(活性)型となる。光産物が安定である場合、光産物が再度光受容すると元の暗状態に戻る。すなわち、暗状態と光産物はそれぞれの光受容により相互変換するので、平衡状態を形成する。光平衡における暗状態と光産物の存在比率は、光の色によって決定する。
※7カルシウムイオン変化のライブイメージング:
カルシウムイオン感受性の蛍光タンパク質であるGCaMPを用い、細胞内のカルシウムイオンのレベルを蛍光強度として画像取得し、解析する方法。細胞内カルシウムの増加と減少は、それぞれ細胞の脱分局と過分極応答を示す。
※8光遺伝学:
光受容タンパク質を細胞に遺伝学的に導入し、その細胞を光により活性化したり制御したりする方法。神経細胞を光遺伝学的に制御することで、行動等の制御も可能となる。
<掲載誌情報>
【発表雑誌】iScience
【論文名】Light intensity-dependent arrestin switching for inactivation of a light-sensitive GPCR, bistable opsin
【著 者】Baoguo Shen, Seiji Wada, Tomohiro Sugihara, Takashi Nagata, Haruka Nishioka, Emi Kawano-Yamashita, Takeaki Ozawa, Mitsumasa Koyanagi, Akihisa Terakita
【掲載 URL】https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111706
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258900422402933X