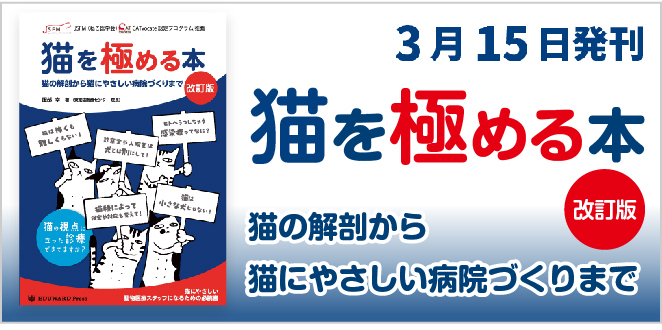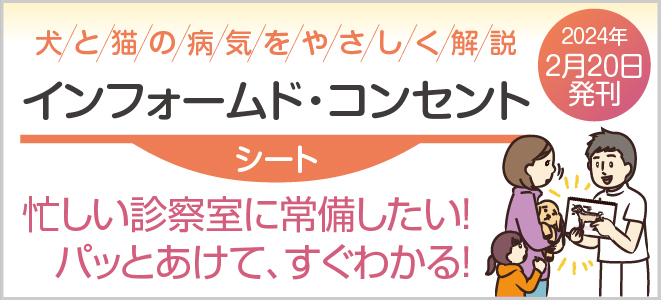JAF(一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳)は10月15日(火)、今年の6月1日(土)~30日(日)にかけて発生した“猫がクルマに入り込んだことによるトラブル”の救援要請件数を発表しました。

ニュース概要
■“エンジンルームに猫”1カ月で381件。12月調査「24件」の約15倍!!
6月1日(土)~6月30日(日)の1カ月間でドライバーから「エンジンルームに猫が入り込んでしまった」とロードサービスを要請いただいた件数は全国で381件ありました。
同様の調査を昨年12月にも実施しており、その際は1カ月間で24件。6月の381件はその約15倍にあたり冬よりも春から初夏にかけての方が猫がクルマに入り込むトラブルが多いことがわかりました。
▼2024年2月21日配信:猫がクルマに入り込んでしまったトラブル1カ月で24件!
https://jaf.or.jp/common/news/2024/20240221-001
猫だけじゃない、意外な動物のクルマ入りトラブル
同調査では猫以外の動物がクルマに入り込んだトラブルも報告されており、同期間で9件ありました。内訳はヘビ6件、鳥2件、犬1件。数字としては決して多くはありませんが、クルマに入り込むのは猫だけとは限りません。エンジンルームなどから物音がして中を確認する際は、ご注意ください。不用意に手を入れてかまれた場合、けがや感染症のおそれがあります。
■事故を防ぐため乗車前にボンネットを優しくたたきましょう。
猫は暖かい場所や狭い場所を好みます。エンジンをかけてしまうとエンジンベルトなどに巻き込まれる場合があり、猫が命の危険にさらされるのはもちろんのこと、クルマの故障(ベルトの切れ、外れなど)にもつながります。猫はドライバーが車内に乗り込んでも気づかないことがあるため、なんらかの方法で猫に人間の存在を知らせる必要があります。
乗車の前はボンネットなどエンジンルーム付近をやさしくたたき、乗車後はエンジンをかける前に数秒静止し猫の気配がしないか確認するなど、できることを実践しましょう。

【参考】
・JAFウェブサイト:クルマ何でも質問箱「猫がエンジンルームに入ることを知っていますか?」
https://jaf.link/3YhiwZ2