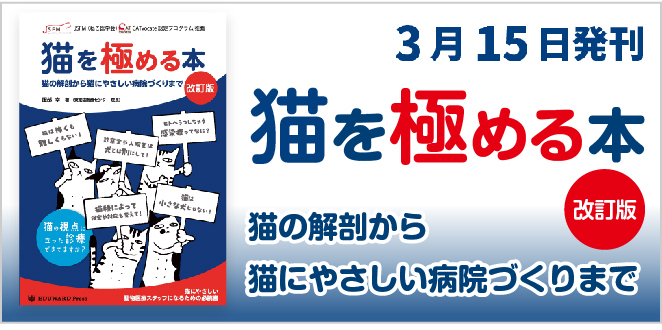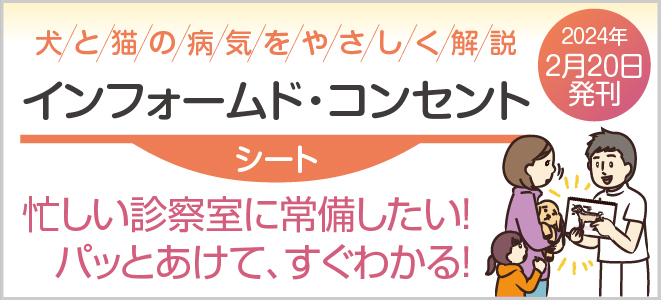●(社福)日本介助犬協会(https://s-dog.jp/)では研修生制度として半年間のOJTによる勤務と研修を行い、新たな人材育成を目指す

ニュース概要
社会福祉法人 日本介助犬協会(以下、協会)では新たな人材育成・確保として研修生制度を導入している。コロナ禍で中断していた研修生募集も2024年度より再開し、今年度は3名の研修生が半年の研修を経て9月30日に研修生を無事に修了している。


研修生を修了した(左から)淵さん、山口さん、山本さん
協会の活動には良質な人材の確保が重要となってくるため、2025年度も引き続き研修生を募集している。
■2025年度研修生制度概要
雇用期間:2025 年4月1日~9月30日(6ヶ月間)
研修内容 :
飼育管理/訓練業務
パピー/繁殖業務
公益業務
広報/総務業務
応募期間:~2024年10月10日(木)
研修場所:介助犬総合訓練センター~シンシアの丘~(愛知県長久手市)
その他募集要項の詳細(協会ホームページ):https://s-dog.jp/archives/info/3336
半年間のOJTによる勤務と研修では、犬のトレーニングに関する訓練業務だけではなく協会の取り組みのひとつである公益業務や広報啓発業務、また総務業務など協会全体の活動について学ぶ機会としている。
■社会福祉法人 日本介助犬協会とは
愛知県長久手市と神奈川県横浜市に拠点があり、全国規模で手足に障がいのある方のサポートをする「介助犬」の普及活動を行っている。また犬たちの個性を活かした活動にも注力しており、人と犬をつなぐ「Dog Intervention®(犬による介入)」の取り組みとして、動物介在活動・動物介在療法、虐待や性被害を受けた子ども達に寄り添う付添犬、そして、発達障がいや知的障がいなど様々な障がいを抱える方のご家族へ犬を譲渡する「With Youプロジェクト」などの取り組みも行っている。
■お問い合わせ
社会福祉法人 日本介助犬協会
045-476-9005
info@s-dog.jp
https://s-dog.jp/