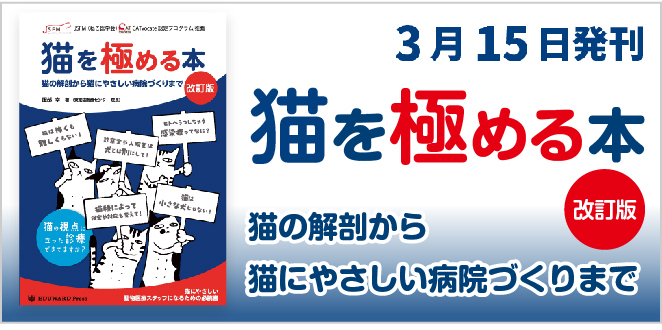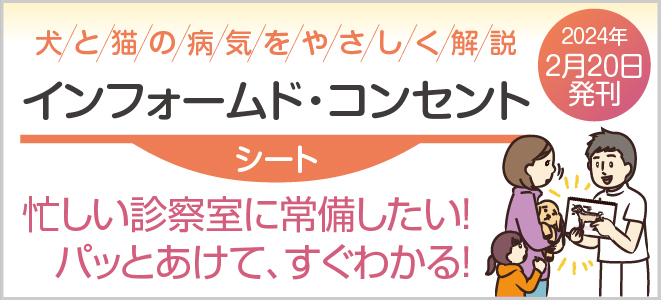イオンペット株式会社(代表取締役社長:米津一郎、以下イオンペット)は、9月11日(水)より、全国約190店舗のペテモ店頭とペテモオンラインストアにて、わんちゃん・ねこちゃん用のクリスマスケーキやオードブル、おせちの早期予約販売を開始します。

ニュース概要
予約販売サイト(ペテモオンラインストア):https://shop.petemo.jp/feature/xmas2024
ペットの「家族化」に伴い、シーズンイベントや記念日をペットと一緒に楽しみたい、ペットの喜ぶ姿が見たいと考えるペットオーナーが増えています。イオンペットが2023年11月に実施したアンケート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000048150.html)によると、ペットと過ごすクリスマスに向けた購入品として、おやつに加え、クリスマスケーキやオードブル、特別なごはんが人気の上位を占める結果となりました。実際にペットオーナーの54.4%がペット用のクリスマスケーキやオードブルを購入経験があるとの回答もあります。
また、今日のペットフード市場では、おいしさと高鮮度・高品質ということに加え、解凍して好きなタイミングで与えられる、冷凍食品の需要が年々拡大しています。
こうした動向を踏まえ、2024年は昨年よりも予約開始時期を約3週間早め、冷凍のわんちゃん・ねこちゃん用のクリスマスケーキ6種類、オードブル4種類、おせち8種類をご用意いたします。
イオンペットは、今後もさまざまな商品やサービスの提供を通し、豊かなペットライフに貢献することで、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。
■販売概要
予約開始日:2024年9月11日(水) ※売り切れ次第終了
店頭お受渡し日:店頭予約の方 12月4日(水)~12月25日(水) ※おせちは12月31日(火)まで
EC予約の方 12月12日(木)~12月25日(水) ※おせちは12月31日(火)まで
※店舗状況によりお渡し日が変動する場合がございます。店頭スタッフまでご確認ください。
予約販売方法:全国のペテモ店頭またはペテモオンラインストア(https://shop.petemo.jp/feature/xmas2024)
■商品詳細(一部抜粋、すべて冷凍)
ペコちゃんのブッシュ・ド・ノエル

★予約受付:店舗・ペテモオンラインストア
★わんちゃん・ねこちゃん用
販売価格:1,480円(税込1,628円)
商品特徴:夢のコラボ!ペコちゃんと仲良しのドッグがクリスマスのケーキを特別に飾ります。ストロベリームースやソースを鮮やかにトッピングし、贅沢なケーキに仕上げました。
コミフ チーズのXmasケーキ

★予約受付:店舗・ペテモオンラインストア
★わんちゃん用
販売価格:1,580円(税込1,738円)
商品特徴:小さめサイズのXmasデコレーションケーキ。ワンちゃんの大好きなチーズダイスを散らし、白色の見た目が冬を連想させるデコレーションケーキに仕上げました。
フルーツたっぷり リースのケーキ

★予約受付:ペテモオンラインストア
★わんちゃん用
販売価格:2,780円(税込3,058円)
商品特徴:極力油分を少なくし、ヘルシーに仕上げました。飾り絞りには、クリームを使用せずマッシュポテトで飾り付け、フルーツをたっぷり乗せた彩りも可愛いクリスマスケーキです。
ねこサンタのムースケーキ

★予約受付:店舗・ペテモオンラインストア
★ねこちゃん用
販売価格:900円(税込990円)
商品特徴:米粉のスポンジにねこちゃんが食べやすいようにいちごムースをたっぷり使い、かわいらしいねこの顔に仕上げた、ねこちゃん用クリスマスケーキです。
犬用 クリスマス&ニューイヤーグルメセット

★予約受付:ペテモオンラインストア
★わんちゃん用
販売価格:3,400円(税込3,740円)
商品特徴:バラエティー豊富なメニューをそろえたグルメなセット。好きなものを選んでクリスマスからお正月までゆっくり楽しんでいただけます。