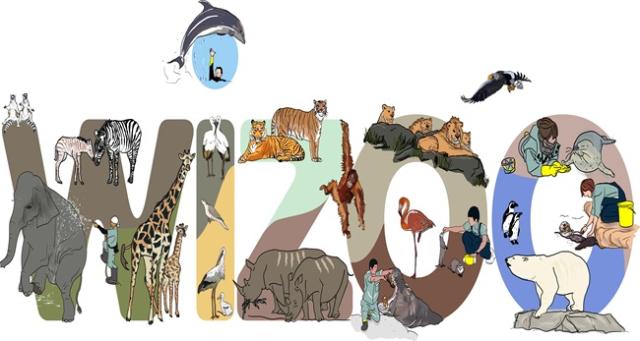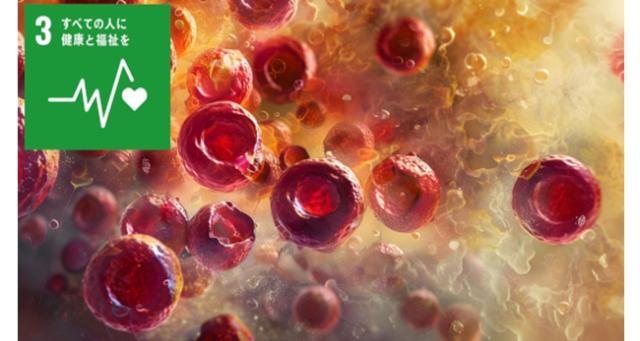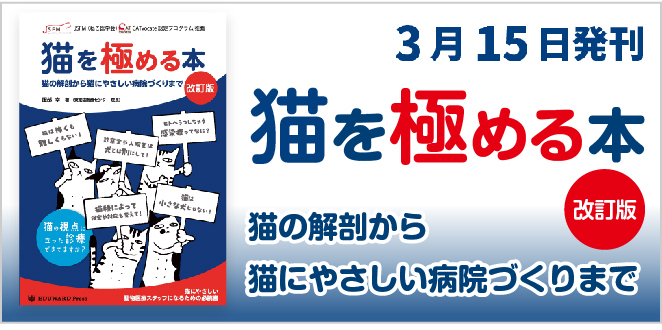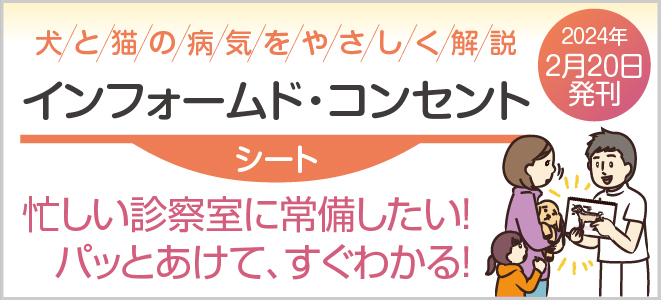株式会社インテージヘルスケア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:村井啓太)と国立大学法人新潟大学(本部:新潟県新潟市、学長:牛木辰男)は、AIを活用したメガリン拮抗薬(※1)の開発に関する共同研究を開始しました。

ニュース概要
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座の斎藤亮彦教授らは、急性腎障害(急性腎障害は、先進国において年間約60万人の死亡、慢性腎不全または慢性腎臓病(CKD)進行に関与している)の発症に関わるメガリンを標的とした創薬研究に取り組んでおり、2024年5月にはメガリンの立体構造とリガンド(※2)結合様式を解明するなど、先進的な成果を公表しております(※3)。
今回の共同研究では、インテージヘルスケアがメガリンの立体構造やリガンド情報を用いて、AI等を使用したインシリコスクリーニング技術により新規化合物の探索・デザインを行います。新潟大学ではデザインされた低分子化合物の評価実験等を行うことで、メガリンを標的とした拮抗薬の創製を目指します。
インテージヘルスケアは、株式会社理論創薬研究所、株式会社アフィニティサイエンスとともに、AIによる新規化合物デザイン、インシリコスクリーニングによる候補化合物探索など、実践的なAI創薬の活用を製薬企業および大学などの研究機関と進めています。この共同研究はインテージヘルスケアが実施する「インテージヘルスケアAI創薬アカデミックプログラム(INTAGE Healthcare AI drug discovery Academic Program:IAAP)」の一環として実施するものです。
※1 メガリン拮抗薬:
メガリンとは、腎臓の近位尿細管細胞に発現する受容体タンパク質で、腎臓に取り込まれる腎毒性物質の「入り口」を司る役割を果たしており、慢性腎臓病(CKD)および急性腎障害(AKI)の予防や治療のための重要な創薬標的として注目されています。メガリン拮抗薬は、腎毒性薬剤のメガリン結合を阻害するもので、広範囲の腎疾患に適応される可能性があります。
※2 リガンド:
化合物のうち、特定のタンパク質を受容体として特異的に結合する性質を持った物質です。
※3 研究成果は、科学誌Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
Americaに掲載されています(doi: 10.1073/pnas.2318859121)
【「インテージヘルスケア AI創薬アカデミックプログラム」について】
AI創薬プラットフォーム「Deep Quartet」などAIによる計算アプローチにより新薬開発の化合物探索及び化合物デザイン等を行い、アカデミアの持つ研究テーマにおいて医薬品候補化合物を見出す共同研究によるスタートアッププログラムです。
【株式会社インテージヘルスケア】 https://www.intage-healthcare.co.jp/
株式会社インテージヘルスケアは、医療・ヘルスケア領域のマーケティングリサーチとデータサイエンスサービスをコアビジネスと位置付けています。インテージグループのヘルスケア領域を担う各社※と一体となり、データ分析・活用によるソリューションを提供。ヘルスケア領域のあらゆる課題に対して、「医療消費者」起点のデータの価値化による、最適な意思決定をサポートしていきます。
※ 株式会社協和企画、株式会社インテージリアルワールド、株式会社プラメド、Plamed Korea Co., Ltd.
【国立大学法人新潟大学】https://www.niigata-u.ac.jp/
国立大学法人新潟大学は、「自律と創生」の理念のもと、教育、研究、社会貢献を通して地域と世界の発展に貢献している大規模総合大学です。「知のゲートウエイ」としてアジアと世界をつなぐ役割を果たすとともに、全学の知を結集して未来のライフ・イノベーションの創出を目指しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社インテージヘルスケア
マーケティング&バリューインサイト事業部
バリュー&アクセス部 創薬支援グループ:村上(むらかみ)
広報担当:深谷(ふかや)・川畑(かわばた)
TEL: 03-5294-8393(代)
E-mail:pr-ihc@intage.com
国立大学法人新潟大学
大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座
特任教授 斎藤亮彦(さいとうあきひこ)
TEL: 025-227-0915
E-mail:akisaito@med.niigata-u.ac.jp