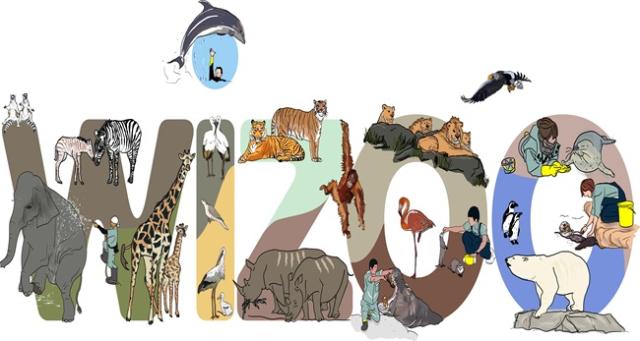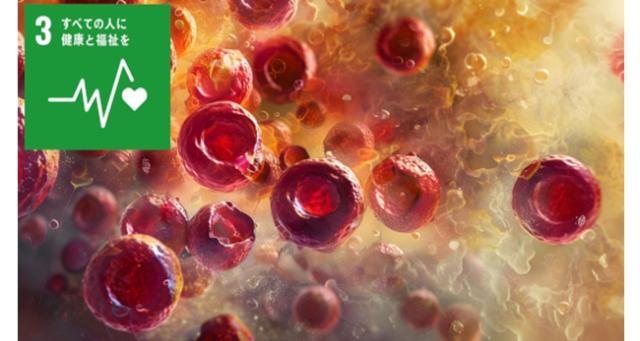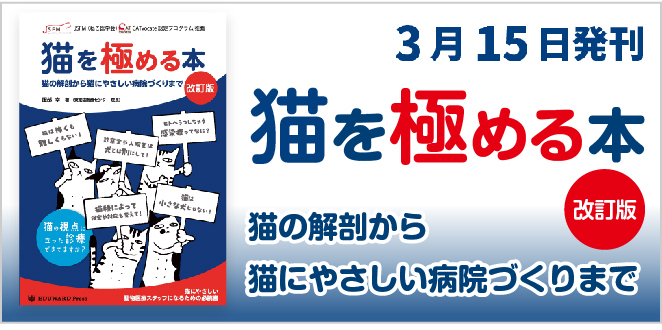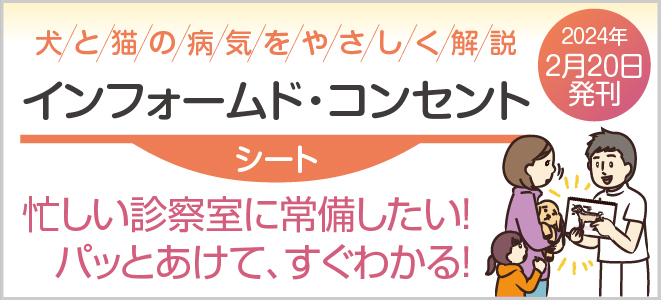ニュース概要
このページでは、当社運営ペット保険メディア全体での契約件数に基づいたランキングをご紹介しています。7月最新版では、2024年6月1日~6月30日の申込み件数を基に集計しています。
《株式会社エレメント》(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:近藤勉)は、ペット保険比較サイト 徹底比較「ペット保険STATION( https://www.pets-station.info/ )」において、【2024年7月最新版】ペット保険おすすめ人気ランキングTOP5を発表いたしました。

■ペット保険ランキング
https://www.pets-station.info/ranking.html
【1位】
アイペット損害保険株式会社 「うちの子」&「うちの子ライト」
https://www.pets-station.info/company_ipet.html
【2位】
ペットメディカルサポート株式会社 「PS保険」
https://www.pets-station.info/company_ps.html
【3位】
SBIいきいき少額短期保険株式会社のペット保険
https://www.pets-station.info/company_sbi.html
【4位】
リトルファミリー少額短期保険株式会社「わんデイズ・にゃんデイズ」
https://www.pets-station.info/company_littlefamily.html
【5位】
ペット&ファミリー損害保険株式会社 「げんきナンバーわんスリム」
https://www.pets-station.info/company_pf.html
■サービス概要
ペット保険 保険料、補償比較 | ペット保険ステーション
https://www.pets-station.info/
人気ペット保険12社の中から「種類・年齢」をもとに保険料・補償内容を比較できる機能をはじめ、高齢ペット向け・多頭飼育向けの条件別比較や、30秒で自分に合ったペット保険を絞り込みできるシミュレーション機能をご案内しています。見積もりから申し込みまで、インターネットで完結するため便利にご利用頂けます。
■人気保険比較サイト
ペット保険: https://www.pets-station.info/
弁護士保険: https://bengoshi-h.info/
自動車保険: https://car-h.info/
自転車保険: https://jitensha-hoken.info/
バイク保険: https://bike-h.info/
妊娠保険: https://ninshin-h.info/
糖尿病保険: https://tonyobyo-h.info/
火災保険: https://kasai-h.info/
■株式会社エレメント
https://element-gr.jp/
当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在は、Web集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業・ネイルサロンの運営など、多角的な事業も展開しております。
■会社概要
https://element-gr.jp/
会社名:ELEMENT GROUP 株式会社エレメント
住 所 :〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町10−4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階
電 話: 03-5428-6601