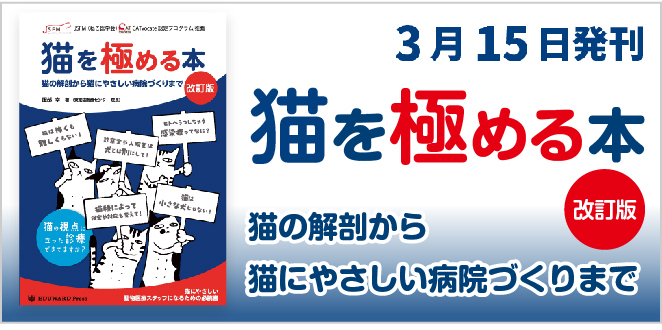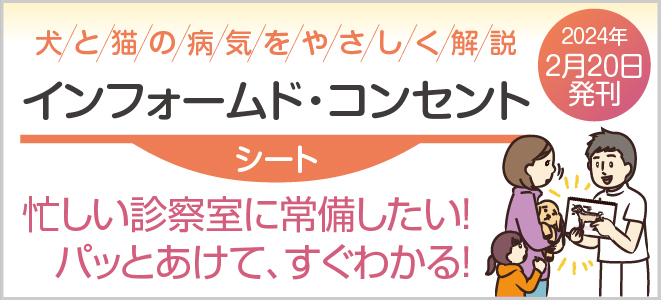ペット保険「PS保険」を提供するペットメディカルサポート株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:米満 明仁)はこの度、全国の20~69歳の犬や猫の飼い主1,095人(有効回答数)にアンケートを実施し、「愛犬・愛猫の肥満対策」に関する実態を調査しました。その結果を、詳しく紹介いたします。

ニュース概要
【調査概要】
期間:2024年4月18日~20日(3日間)
対象:全国の20~69歳の犬や猫の飼い主
方法:インターネットリサーチ
有効回答数:1,095(調査の対象となったのは3,007人で、36%にあたる1,095人から回答を得ました)
※本集計データを引用する場合は、出所元として「ペット保険『PS保険調べ』」と明記をお願いします。
【調査結果:愛犬・愛猫の肥満対策に関する実態】
愛犬・愛猫を食いしん坊と感じている飼い主は、半数以上。
飼い主の32%が愛犬・愛猫を「太り気味」と思っている。
愛犬・愛猫が太り気味の理由は、フードやおやつの食べすぎ。
飼い主の6割以上が愛犬・愛猫の摂取カロリーを気にしている。
「人間の食べ物を与えない」、「低カロリーのフードを与える」などで肥満を対策。
※本集計データは小数点以下第1位を四捨五入しているため、集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。
※グラフ内に「複数回答可」と記載している設問は、設問に対する回答者数を分母として選択肢ごとの割合を算出しているため、集計値の合計が100%を超える場合があります。
飼い主の半数以上が愛犬・愛猫は食いしん坊と感じている
愛犬・愛猫に食欲があることは元気な証拠であり、食いしん坊な姿を愛らしく感じることもあるでしょう。一方で、愛犬・愛猫の健康や食費を考えると、注意しなくてはなりせん。
今回のアンケートでは、現在飼っている愛犬・愛猫を食いしん坊だと思っている飼い主は55%(「かなり食欲がある」30%と「やや食欲がある」(25%)との合計)いることがわかりました。また、愛犬・愛猫の食欲を「適度」と思っている飼い主は37%いるという結果になり、反対に愛犬・愛猫の食欲不振を認識している飼い主は少数派でした。

愛犬・愛猫が太り気味と思っている飼い主は32%
愛犬・愛猫の体型を「理想体型」と回答した飼い主が54%で最も多くなりましたが、32%は「太り気味」と回答しています。また、「太りすぎ」と回答した飼い主も4%いました。
この結果から、愛犬・愛猫が太り気味、または太りすぎと認識している飼い主は全体の3分の1を占め、決して少なくないことがわかります。

フードやおやつの食べすぎが太り気味の理由に
愛犬・愛猫が太り気味、または太りすぎの理由としては、「フードの食べすぎ」が最も多く挙がり(33%)、次いで「おやつの食べすぎ」(28%)という結果になりました。
多くの飼い主は、愛犬・愛猫が太っている原因として、運動量の少なさよりも、主食や間食の摂取量に問題があると考えています。散歩や室内での運動でしっかり体を動かしているとしても、そもそも食事量が多いと体型に影響が出てしまうようです。

飼い主の6割以上が愛犬・愛猫の摂取カロリーを気にしている
愛犬・愛猫の摂取カロリーを「かなり気にしている」(13%)、「やや気にしている」(49%)と回答した飼い主は合わせて全体の62%という結果になり、食事の管理は飼い主が気をつかうポイントであることがわかりました。
こうした傾向は、近年、カロリーオフをうたうペットフードの種類が増え、それが店頭やECサイトなどで目につきやすいからかもしれません。

愛犬・愛猫の肥満対策は「人間の食べ物を与えない」が最多
愛犬・愛猫の肥満対策には「人間の食べ物を与えない」(35%)、「低カロリーのフードやおやつに変える」(29%)、「食事量を減らす」(25%)が多く挙がりました。
多くの飼い主は、愛犬・愛猫がフードやおやつの食べすぎで太っていると考えています。しかし、実際には、肥満対策としては低カロリーのフードやおやつに変えるよりも、人間の食べ物を与えない方法を選んでいることがわかります。
飼い主が食べているものを欲しがる愛犬や愛猫は珍しくありませんが、人間の食べ物には脂質や糖分が多く含まれ、犬や猫にとってはカロリー過多になるおそれがあります。カロリー過多による肥満を防ぐには、愛犬・愛猫におねだりされても人間の食べ物を与えないようにし、食事管理を徹底する必要があるでしょう。

愛犬・愛猫が肥満にならないように適切な食事管理を
今回のアンケートでは、愛犬・愛猫がペットフードやおやつなどの食べすぎによって、太り気味であると考える飼い主が少なくないことがわかりました。
愛犬・愛猫の摂取カロリーに気を配り、さまざまな肥満対策に取り組む飼い主は多いようです。しかし、食事だけでなく、運動量も含めて総合的に体型をコントロールすることが重要です。
愛犬・愛猫の食事管理に悩むことがあれば、かかりつけの動物病院に相談するのもおすすめです。人間と同様に、犬や猫も肥満はさまざまな疾患を引き起こすおそれがあります。そのため、愛犬・愛猫のダイエットが思いどおりに進まない場合や食欲が収まらない場合は、早めに専門家のアドバイスをもらうといいでしょう。
ペットメディカルサポートのペット保険「PS保険」は、軽微な通院治療から手術をともなう入院まで幅広く対応しています。お手ごろな保険料で十分な補償が受けられるうえ、保険料の引き上げ(※1)は3歳ごとに1度とゆるやかなので、生涯にわたり無理なく続けやすいペット保険です。
※1 将来の保険料を約束するものではありません。
■ペット保険商品「PS保険」の特長
https://pshoken.co.jp/summary/
PS保険では保険による補償以外に、契約者さまへのサービスとして、経験豊富な獣医師に24時間365日電話相談できる「獣医師ダイヤル」を無料(※2)で提供しています。かかりつけの動物病院の診察時間外の時なども、すぐに相談できて安心です。
※2 通話料はお客さまのご負担になります。
■24時間365日対応 獣医師ダイヤル
https://pshoken.co.jp/summary/veterinarian_dial.html
【会社概要】
商号 : ペットメディカルサポート株式会社
代表者 : 代表取締役社長 米満 明仁
所在地 : 〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス2階
営業開始日: 2008年5月2日
事業内容 : 少額短期保険業(登録番号 関東財務局長(少額短期保険)第24号)
資本金 : 3億3,275万円(2023年3月時点)
URL : https://pshoken.co.jp/