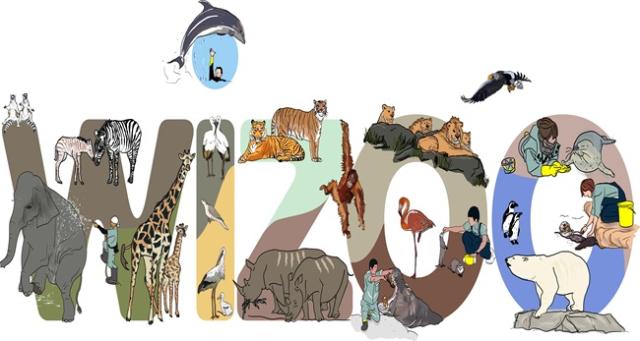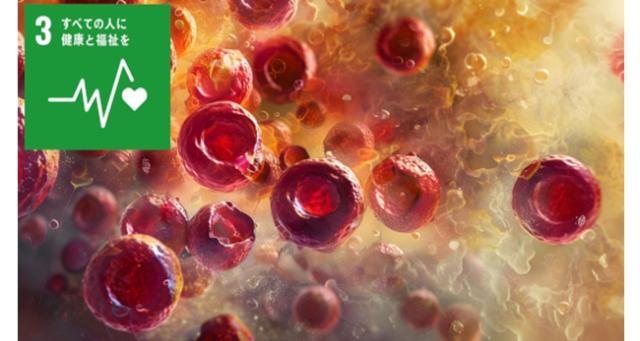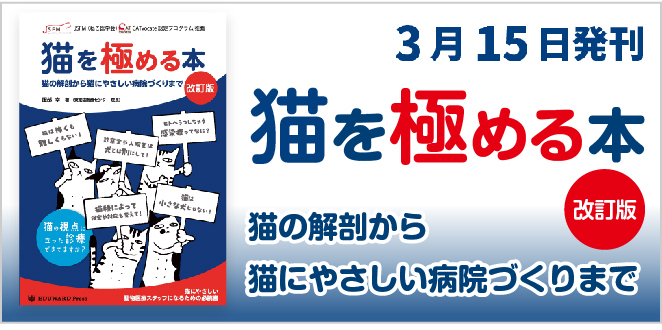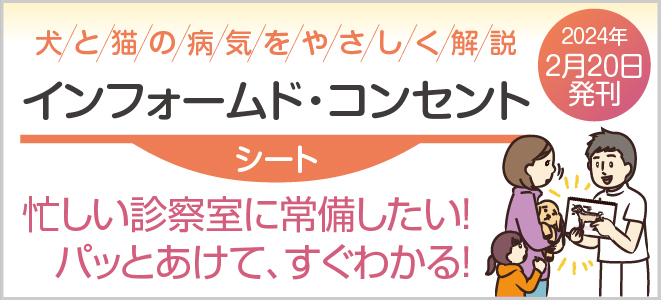全国にペットショップ「Pet Plus(ペットプラス)」を運営する株式会社AHB(所在地:東京都江東区、代表取締役:川口 雅章、以下「当社」)は、「動物と人間の幸せな共生社会の実現」との企業理念に基づき、新たな飼い主様と出会うまでの子犬・子猫の飼育環境の向上に尽力しております。
そしてこの度、全国のペットプラス134店舗の子犬・子猫の食事に、フレッシュペットフードを導入したことをご報告します。

ニュース概要
◾️ フレッシュペットフードの導入
当社は成長期である子犬・子猫が健康に育つため必要な栄養素を担保するため、食事面への管理を重視してきました。これまで、総合栄養食のドライフードをメインに、必要な食事量を適切に与えるための独自システムを開発する等、徹底した食事管理を行っております。その他にも月齢や成育状況、体調に応じ、様々な工夫や配慮等を行ってきました。
そして今回、更なる子犬・子猫の健康的な食事管理を目指すため、フレッシュペットフードの導入を決めました。
フレッシュペットフードはアメリカで愛犬家を中心に広がりつつある新しいフードカテゴリで、ヒューマンクオリティの食材を使用し、食材本来の栄養素を生かして冷凍処理を行うことで新鮮な状態で食べられることが特徴のフードです。
当社は、体の土台を作る幼齢期こそ食事を見直すべきだと判断し、さまざまなフードの検証を行いました。現在も試行錯誤を行っている中ではありますが、日本でフレッシュペットフード普及をリードする「ペトコトフーズ様」に協力いただき、全国の当社店舗で導入を行いました。
日々、当社の子犬・子猫を診察する獣医師からは、「ふやかしたフードを食べなかった子が、フレッシュフードをトッピングすることで食欲が増し、トッピングだけでなくふやかしたフードも食べてくれることが増え安定的に完食している」「食事への興味関心が高くなった」等の声が寄せられています。

<当社獣医師より>
毎日の食事は、私たちが新たな飼い主様に送り出した後の、長い犬生・猫生を過ごす体をつくる非常に重要な行為です。今回、フレッシュペットフードの導入にあたり、当社の管理コストは必然的に高まるものの、子犬・子猫や飼い主様にとって、それを上回るメリットがあると感じています。食事を自分でしっかりとることは、子犬・子猫の生命維持と健康増進にとても重要なことであるため、食欲を刺激してくれる美味しいフレッシュペットフードを今後も活用していきたいと考えております。
そして、品質かつ栄養満点のフレッシュペットフードを通じて、子犬・子猫と飼い主様の双方に幸せをお届けするとともに、今後も様々な取り組みを通じて、ペット業界のスタンダードを良い方向へと変えていけるよう尽力していきます。
株式会社AHB 獣医師 只野 萌
◾️ 受け入れ体制
当社は、当社の受け入れ基準を満たした、優良ブリーダー様からのみ受け入れております。そして、受け入れた子犬・子猫は全頭、全国6ヵ所に開設しているウエルネスセンターにて、当社専属獣医師による診察や愛玩動物看護師等による健康管理を実施し、子犬・子猫とその飼い主様が健やかに、幸せな毎日を過ごすための基盤を確立しております。
◾️ お迎え後の幸せのために
「幸せ配達人」である当社従業員は、専門家の知見を取り入れた各種教育プログラムの受講をはじめ、プロフェッショナルな人材へと育成するために必要な社内外の資格を取得する等、子犬・子猫と飼い主様へのサービスクオリティの向上に努めております。
また、特許取得済みの展示スペースである「プレイルーム」は、子犬・子猫の性格を形成するうえで非常に重要な社会化期に同じ種別同士で触れ合いながら、快適に過ごすことができる構造となっております。
さらに、人間との共生にあたり、電話の呼び出し音や掃除機の音等、様々な音に慣れるための「生活音トレーニング」や、褒めながら楽しく教える「トイレトレーニング」など、子犬・子猫の健康と快適さを第一に考えたうえで、お迎え後の飼い主様との生活にもスムーズに溶け込めるよう、幸せ配達人が愛情をもって接しております。

詳しい取り組みはこちら|https://www.ahb.jpn.com/effort/shop
◾️ 動物福祉への取り組み
当社は、動物愛護団体(NPO等)と連携し物品の支援や去勢・避妊の実施等、生涯にわたる幸せなペットライフに向けたサポートをはじめ、人と動物の共生に関わる各分野の動物愛護・保護活動に関して造詣が深い専門家を招いたアドバイザリーボードを設置し、動物福祉の観点に寄り添った事業運営に繋がるよう取り組んでおります。
関連ニュースリリース|当社アドバイザリーボードの設置概要
https://www.ahb.jpn.com/press_releases/6199
また、社会のセーフティーネットとして活動する保護団体様への訪問・意見交換を行い、共に動物福祉活動を積極的に推進しております。
関連ニュースリリース|認定特定非営利活動法人キドックス様 訪問記録
https://www.ahb.jpn.com/press_releases/11977

今後も、ペットを取り巻く社会課題に真摯に向き合い、解決に向けて全力で取り組んでまいります。

◾️ 当社の事業について
当社は、ペットショップ「ペットプラス」と「ペットプラストリミングサロン」を中心に、犬と猫に関する事業を全国に展開しております。また、ブリーディングから引退した犬や猫のセカンドライフを見つけるための取り組み「パートナードッグ&キャットプログラム」や、遺伝子病のない世界を実現するため、受け入れた子犬・子猫全頭に「遺伝子病検査」を実施する等、徹底した健康管理を通じて、人とペットのより良い関係の構築と幸せなペットライフをお届けすることを目指しています。
<会社概要>
会社名 : 株式会社AHB
代表者 : 代表取締役 川口 雅章
所在地 : 東京都江東区木場三丁目7番11号
設立 : 2011年10月11日
店舗数 : 全国164店舗(トリミングサロン・AHBASE・動物病院を含む)
資本金 : 3,000万円
URL : https://www.ahb.jpn.com/