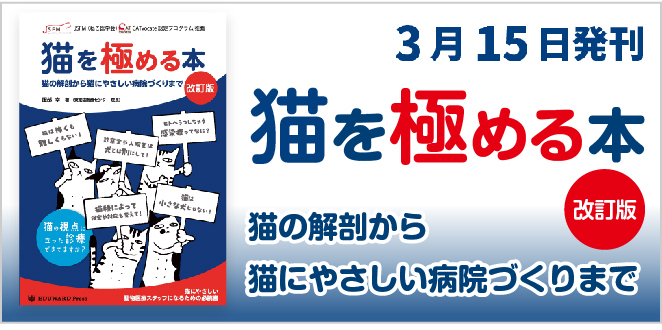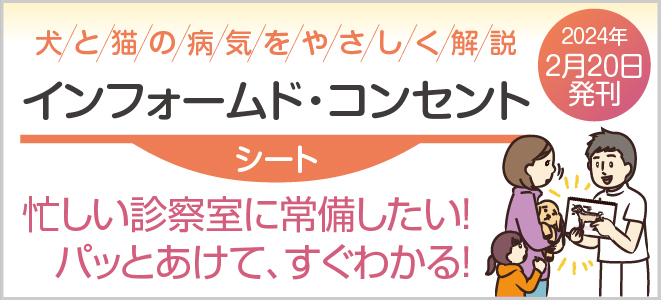株式会社SaLaDa (本社:東京都港区、代表取締役社長:佐藤拓矢)は、大阪ECO動物海洋専門学校にて、2024年4月より産学連携教育としてゼミを開講いたします。
ゼミでは、2年生を対象とし、マイクロブタさんを介在させる活動が人間の心身の健康や教育に果たす役割について学習を行います。ブタさんへの倫理的配慮を重視した活動が、人と動物双方の福利向上に貢献するという考えのもと、mipig cafe 大阪店やmipig cafe 京都店での店舗実習のほか、幼稚園や福祉施設へのアニマルセラピーも実施予定。ブタさんを介在した接客スキルを上げると共に、動物福祉や動物の行動やトレーニングについても学びます。

「行動」に重きをおく授業スタイルで、物事を多角的に捉え、考え、行動し、社会で活躍できる人材に成長できるようなプログラムを予定しています。mipigのミッションである「with pig -ブタさんとヒトが幸せに共生できる未来の実現-」を目指し、様々な角度から一緒に、ブタさんとヒトの共生について議論を深めてまいります。
本ゼミの開講にあたり、学生にとっても学びの時間であることをご理解いただいた上で、大阪府内の教育施設・福祉施設から、アニマルセラピー実施希望施設を募集いたします。ご興味のある施設の方はぜひ、お問合せフォームより必要事項を回答の上、エントリーください。

ニュース概要
■講師紹介

北川 史歩 / 株式会社Hooome 取締役
2018年グロービス経営大学院在籍中、日本初のマイクロブタカフェ「mipig cafe(マイピッグカフェ)」の立上げに参画。現在、「マイクロブタ研究会」を発足し、医療・教育・福祉の確立に向け、奮闘中。

守谷 里砂 / 株式会社Hooome cafe事業部 関西エリア マネージャー
2019年、大阪ECO動物海洋専門学校卒業後、岩手サファリパークを経て、2020年9月、mipig cafe 大阪店の立上げメンバーとして参画。大阪店店舗責任者、札幌発寒店の立上げ後、関西エリアマネージャーに。ブタさんのトレーニングを得意とする。
■大阪ECO動物海洋専門学校
建学の理念(実学教育、人間教育、国際教育)を実践し、動物・海洋・ペットの分野で社会貢献できる人材を育成するため、1998年に日本で初めて認可を受けた動物分野の学科を扱う専門学校として設立される。毎年動物業界への高い就職実績を実現し、日本全国で卒業生が活躍する大阪ECO。校舎内の動物園・水族館では150種類500頭羽以上の動物を飼育し、プロによる授業や企業と連携した実践授業で動物業界への就職に導き、高い就職率を誇る。
■カリキュラム内容
カリキュラムの内容は、下記内容にて実施予定。
①mipig cafe での研修
②アニマルセラピーの活動
③動物の福祉
■アニマルセラピー実施希望施設(大阪府内)募集
アニマルセラピー実施希望施設の方は、以下より申込ください。
【実施概要】
期間 :2024年6月~12月の水曜日(※8月は夏休みのため活動休止)
費用 :実費(交通費)
時間 :10:00-17:00内(人数により、時間調整いたします)
同行者 :ブタさん 3-5匹 , スタッフ 4-5匹
申込 :https://forms.gle/3p6u9hsdrArKMj9N8