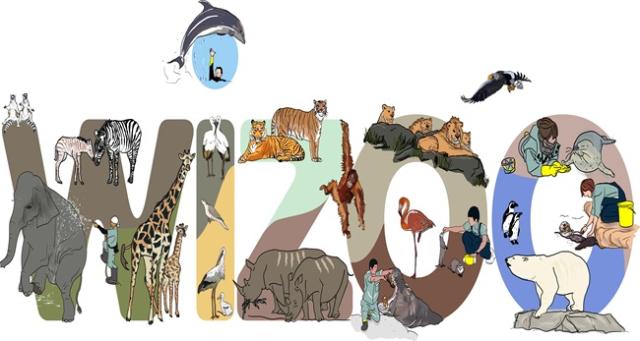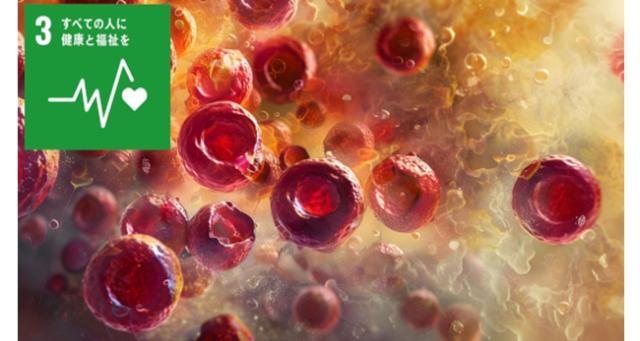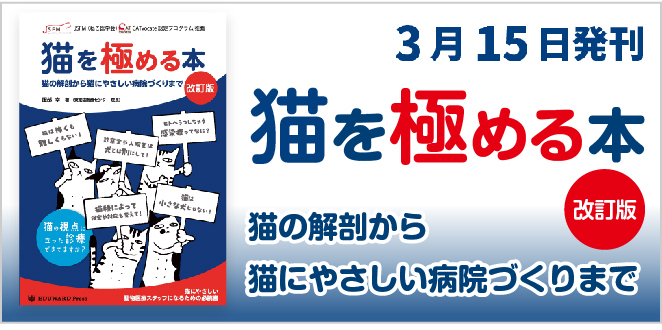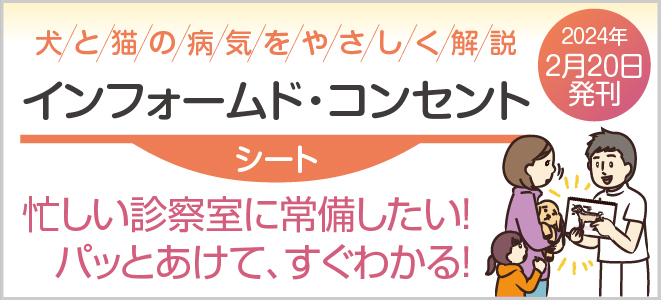こんにちは、エデュワードプレス求人事務局です。
今回のコラムでは、求人や採用をおこなう際、参考として『有効求人倍率』をご紹介します。
獣医師、動物看護師の求職と求人のバランスや、就業者数や失業率などの統計情報など。雇用情勢についても調べてみましょう。
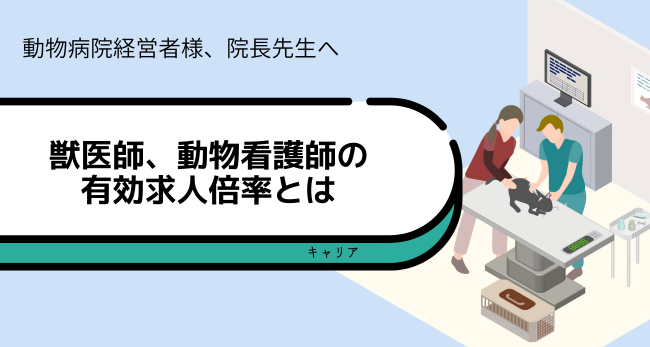
◆求職と求人のバランス
厚生労働省が毎月取りまとめている『一般職業紹介状況』によると、2024年1月の全業種の数値は、有効求人倍率は1.27倍となっています。コロナ禍の影響で令和2年より著しく下がった有効求人倍率ですがその後、令和4年頃より比較的安定した水準を保っています。
有効求人倍率とは、1人の求職者に対し何件の求人があるかということになります。
数値が高くなるほど求職者は選ぶ求人が多く就職先を選びやすい傾向です。
獣医師は、同一般職業紹介状況の中では、「専門的・技術的職業従事者」の項目で「医師、歯科医師、獣医師、薬剤師」にカテゴライズされており、その有効求人倍率は2.35倍となっています。
ただ、これだけでは4業種の数値のためもう少し詳しく探してみると、厚生労働省が運営する『職業情報提供サイト』でハローワーク求人統計データというものがあります。これによると獣医師単独の有効求人倍率は「1.70倍」となっています。
獣医師、動物看護師の個別の有効求人倍率や就業人数、労働時間、賃金、年齢等の数値に関しては、この『職業情報提供サイト』にて公開されていますので、ご参考になさってください。
以下、令和6年3月28日時点での情報です。
【獣医師】
就業人数:24,680人(出典:令和2年国勢調査の結果を加工して作成)
労働時間:169時間(出典:令和4年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)
賃金:年収686.6万円 月額33.5万円 ( 〃 )
年齢:37.8歳( 〃 )
有効求人倍率:1.70倍
出典:職業情報提供サイト「獣医師」
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/223
この就業人数は国税調査結果によるもので、農林水産省で取りまとめられている獣医師の届出数は、40,455人(令和4年12月31日時点)となります。
【動物看護】
就業人数:167,460人(出典:令和2年国税調査結果を加工して作成)
労働時間:169時間(出典:令和4年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)
賃金:年収312万円 月額18.9万円 ( 〃 )
年齢:35.7歳( 〃 )
有効求人倍率:1.45倍
出典:職業情報提供サイト「動物看護」
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/510
愛玩動物看護師の人数は、2024年3月1日時点で登録者数17,342名。
第2回の国家試験合格者は4,666人となっています。
2024年4月1日には、今回の試験合格者からも登録者がプラスされていくことでしょう。
これら有効求人倍率に関しては、獣医師・動物看護師ともに1.5倍前後。
1人に対して求人が1.5件程しかないということなので、平均値よりは多い状況です。
求人掲載をする側としては、有効求人倍率が低いときに求人を出すことで見てもらう確率が上がります。
倍率が多いときには、より自院を選んでもらいやすいように求人サイトや求人媒体でのアピールを強化する必要があります。
参考)
厚生労働省 職業安定業務統計:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1b.html
厚生労働省 職業情報提供サイト:https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/223
求人サイトEDUONE Career 掲載はこちらから
https://career.eduone.jp/ah