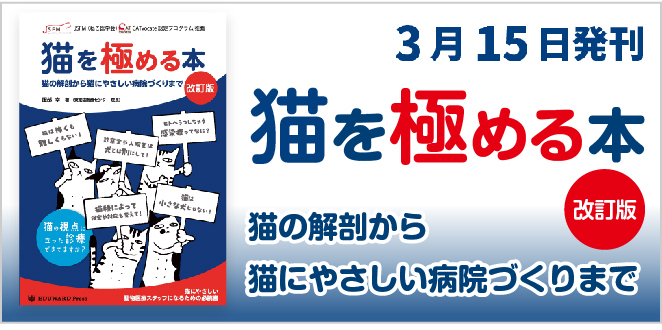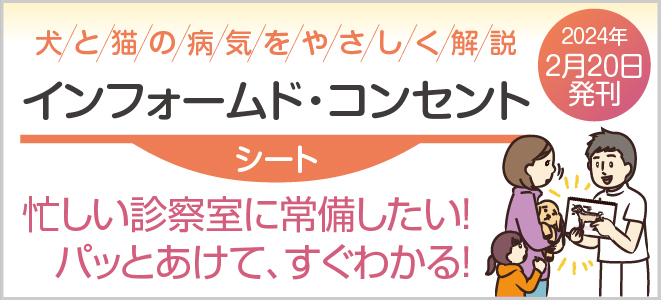質量分析技術による細菌同定の概要と応用
質量分析技術による細菌同定への応用は、1975年から始まり、1980年代になりMALDI-TOF MSの開発に伴って急速に普及してきたました。質量分析はタンパク質などの分子の重さを計ることで、未知の試料にどのようなタンパクがどのくらい含まれているかを知るものです。試験菌のスペクトルを既存のデータベースと比較することで同定します。実際には、検査する細菌のコロニーの一部をMALDIプレートに塗布し、マトリックスを加えてイオン化し、真空中のある一定の距離をイオンがどのくらいの時間で飛ぶかを計測して質量を求めるものです(図1)²⁾。また、MALDI-TOF MSの原理³⁾を図2に示しましたので参考にして下さい。
▼図1.MALDI-TOF MSによる細菌同定手順の概要²⁾
https://www.eiken.co.jp/uploads/modern_media/literature/2017_03/003.pdf


▲図2.MALDI-TOF MSによる細菌同定法の原理³⁾
この技術の発端に成ったのは2002年にノーベル化学賞を受賞した田中耕
一先生(島津製作所)が開発した「生体高分子の質量分析法のための脱離イオン化法」の技術であり、この分野に対して日本が大きく貢献したことになります。
細菌に由来したタンパク質成分は菌種によって特徴的であり、各種細菌のタンパク質の分子量情報のパターンから、MALDI-TOF MSではわずか5分足らずで細菌の同定ができるという画期的な技術です。ただ問題点としては装置が非常に高額(1000~5000万円)であることや、菌種に関するデータが医学細菌に偏っており、動物由来細菌や環境細菌などは現時点で同定できない菌種が多く含まれていることなどです。しかし、最近では動物由来細菌のデータベースは充実したものになっています。
例えば、犬の膿皮症の主な起因菌とされるメチシリン耐性Staphylococcus pseudintermediusは、これまで臨床検査会社に依頼すると生化学性状からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)と誤同定されることが報告され⁴⁾、遺伝子検査でしか正確に同定できませんでした。最近、データベースが完備し、MALDI-TOF MSで確実に同定できるようになりました。今後、動物あるいは環境由来細菌の情報が集積することにより、医学以外の分野での応用は格段に増加するものと考えます。
さらに迅速性が求められる血液培養液から直接同定作業に入る方法⁵⁾や、尿路感染症の診断においても一定量以上の菌体量があれば直接同定が可能との報告もあります⁶⁾加えて、臨床細菌学では必須の薬剤感受性試験も、MALDI-TOF MSでの応用研究も盛んに行われています。細菌の産生するβ-ラクタマーゼによるβ-ラクタム薬の分解物を検出することで間接的に薬剤耐性の有無を評価するなどです⁷⁾。まだ実用化段階ではないものの今後の応用が期待されます。