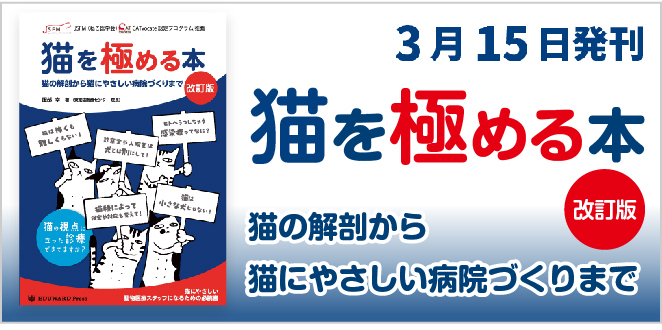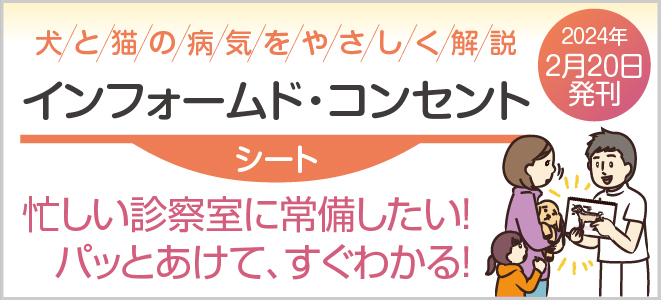■はじめに/読者の皆様へ
皆さん、初めまして。酪農学園大学の田村 豊と申します。
今年の9月まで獣医学群食品衛生学ユニットに所属し、獣医学生に対して獣医公衆衛生学の教育と、
動物と環境由来薬剤耐性菌の分子疫学に関する研究に従事していました。
今回、縁あってEDUWARD MEDIAにおいて獣医学関連の最新の話題について
「今週のヘッドライン 獣医学の今を読み解く」と題して
シリーズでコラムを書かせていただくことになりました。
大学の講義の最初に「今週のヘッドライン」として話していた、獣医学関連の話題を継承するものです。
毎週のように獣医学関連のニュースが引きも切らずに国内外から公表されています。
今回は読者が小動物医療関連の獣医師や動物看護師が中心ということで、
小動物医療関連の話題を中心に解説していきたいと思います。
また、獣医学全般の話題でも皆さんに知っておいて欲しいものも取り上げます。
世界で刻々と動いている獣医学の今を肌で感じていただければ幸いです。
是非とも興味を持っていただき、継続してお読みいただけることを期待しています。
酪農学園大学名誉教授 田村 豊

はじめに
2021年6月4日に滋賀県はオウム病の集団発生疑いの事例について公表しました¹⁾。具体的には4月6日に同一職場内において発熱等の症状を複数名の者が呈していることから、国立感染症研究所に確定診断のための検査を依頼していたところ、6月4日にオウム病と判明したものです。今般の事例では確定例2例で、発熱および肺炎の症状を示す可能性例7例、38℃以上の発熱の症状のある疑い例6例を含むオウム病による集団発生(疑い)の発生事例として公表されたものです。なお、建物の入口に野生のハトの糞が積もっていたとの 情報があり、県はこれが感染源でないかと推定しています。オウム病は鳥類が感染源として重要な人獣共通感染症であり、これまでわが国で死亡例も報告されていることから、ここで今一度知識を整理するために概要を紹介したいと思います。