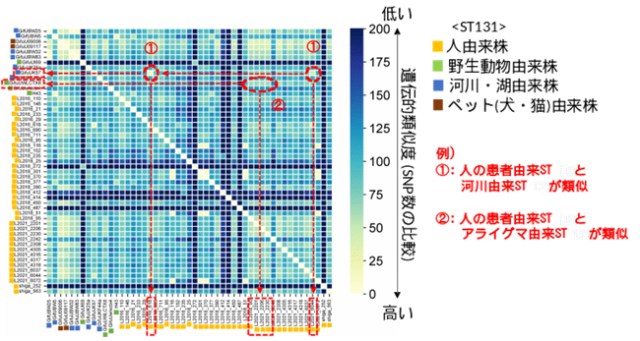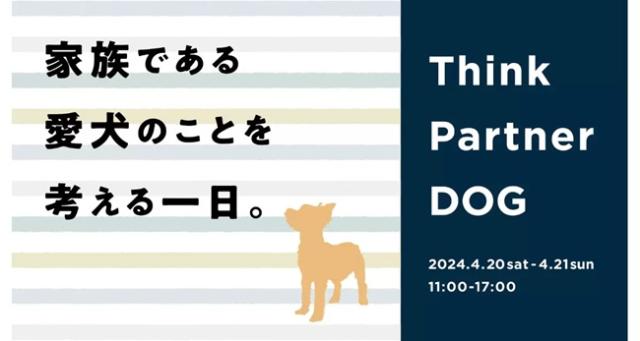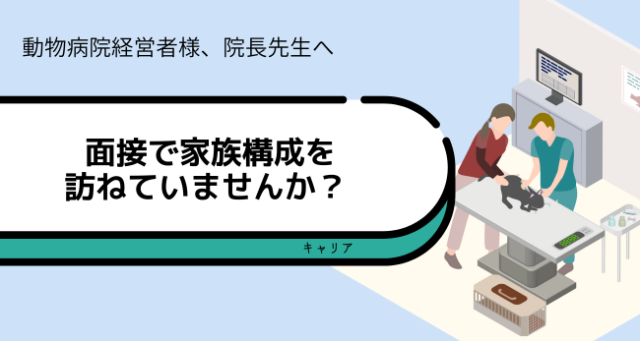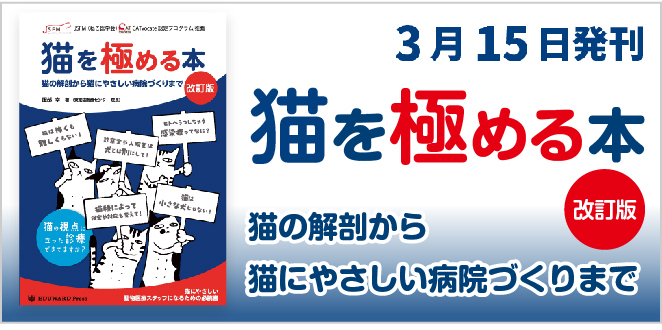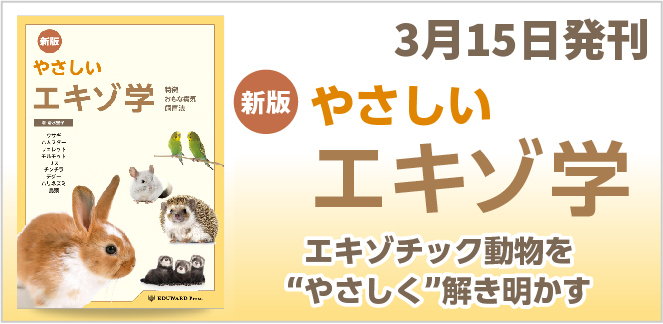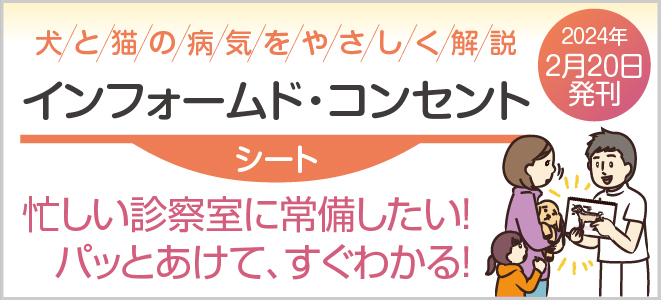兼松株式会社(以下、「兼松」)とデンマークのDANISH CROWN A/S(以下、「DANISH CROWN」)は、日本市場においてサステナブルな豚肉製品の販売を促進するための、基本合意書を締結しました。
本合意により、DANISH CROWNの「サステナブルな食肉生産への取組み」と、兼松が長年にわたる畜産事業で築いた「日本市場における多様な流通チャネル」を組み合わせ、持続可能性に焦点を当てた、戦略的なパートナーシップを確立します。従来のおいしさ・高品質に加えて、地球環境やアニマルウェルフェア(動物福祉)に配慮して生産された豚肉製品を、日本全国のお客さまへ提供し、持続可能な社会の実現に貢献して参ります。

ニュース概要
DANISH CROWNは欧州最大規模の食肉加工企業で、兼松とは約40年にわたって信頼関係と取引実績を積み重ねてきました。同社の重要市場の一つである日本市場において兼松は最大の取引先であり、事業パートナーです。今回の連携により、DANISH CROWNや顧客企業と共にサステナブルな食肉のサプライチェーン構築を促進し、日本における消費者のサステナビリティ志向の高まりに応える態勢を整えます。
また、同社は大規模な投資を通じて、「最もサステナブルな食肉生産」を探求している業界のリーディングカンパニーです。目標の一例として、2030年までに食肉生産による温室効果ガス排出量の50%削減(2005年比)、2050年までのカーボン・ニュートラル達成を目指しています。さらに、環境への配慮として食肉生産で発生するメタンガスの削減や、アニマルウェルフェアの向上など様々な取組みを行っています。
兼松は、畜産業界においてトップクラスの市場シェアを有し、長年にわたり培った、豊富な知見と商品群を有しております。今回の合意によりDANISH CROWNのサステナブルな取組みを付加価値として、日本のお客さまへCFP(カーボンフットプリント)※1の提供や、製品のマーケティング・コミュニケーションの共同検討などを推進し、更なるシェア・商品群の拡大を目指します。そして環境目標を掲げる顧客企業の目標達成への貢献や、ひいては日本の豚肉業界において、持続可能性に配慮した製品を取り扱う慣行作りに繋げて参ります。
※1 商品のライフサイクル全般(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)で排出された温室効果ガスをCO₂量で表したもの
【各社代表者コメント】
兼松株式会社 代表取締役社長 宮部 佳也

約40年にわたり、DANISH CROWNと兼松は、日本の食肉市場に優れた品質と高い安全性の製品を提供する為に連携して参りました。今回のパートナーシップによって、おいしさや品質・安全性だけでなく、改めてサステナビリティに焦点を当てることで、より地球の未来に貢献できる製品を、お客さまに提供できることを嬉しく思います。
今回の合意は、「高品質で、持続可能な食品の選択肢を消費者に提供する」という私たちの使命において、重要な一歩であると考えております。
DANISH CROWN /CEO Jais Valeur

We are thrilled to strengthen our partnership with Kanematsu by adding sustainability to our longstanding commitment to quality and safety, and I commend Kanematsu for taking this bold step with us. The green transition of the food industry is essential for Danish Crown, and our business strategy builds on substantial sustainability investments. This strategic agreement not only reflects our dedication to environmental stewardship but also ensures that our products meet the evolving needs of our discerning customers in Japan. Achieving our sustainability ambitions is not possible without the support of our customers. Their commitment to integrating sustainability into their business operations is a testament to the shared vision we hold for a more sustainable future in the food industry.
品質と安全性に対する長年の取組みにサステナビリティを追加することで、兼松とのパートナーシップを強化できることを嬉しく思います。食品業界のグリーン化はDANISH CROWNにとって不可欠であり、当社の事業戦略は多額の持続可能性への投資に基づいています。この戦略的合意は、当社の環境に対する責務を反映しているだけでなく、当社の製品が、日本の目の肥えたお客さまの進化するニーズに応えることを保証します。 サステナビリティに関する目標達成は、お客さまのサポートなしには不可能です。サステナビリティを事業運営に取り入れるという兼松のコミットメントは、食品産業における持続可能な未来のために、私たちが共通のビジョンを有している証です。
■ DANISH CROWN会社概要
商号: DANISH CROWN A/S
設立: 1887年
代表: Jais Valeur, Group CEO
所在地: Danish Crown Vej 1, DK-8940 Randers SV
事業内容: 豚・牛の屠畜・加工、食肉製品・食肉加工品の製造販売 ほか
ウェブサイト: https://www.danishcrown.com/global/