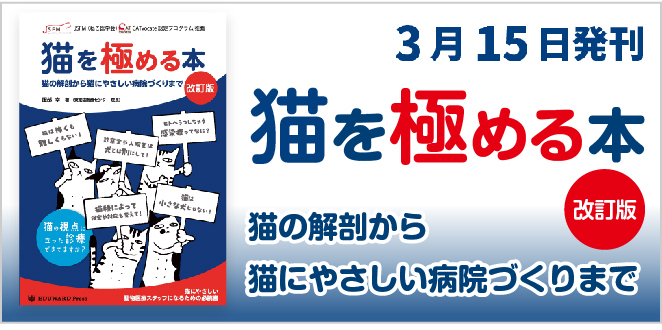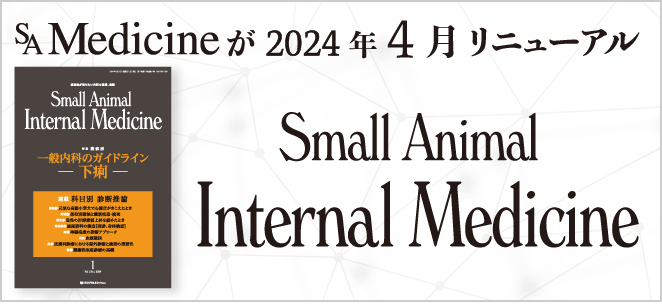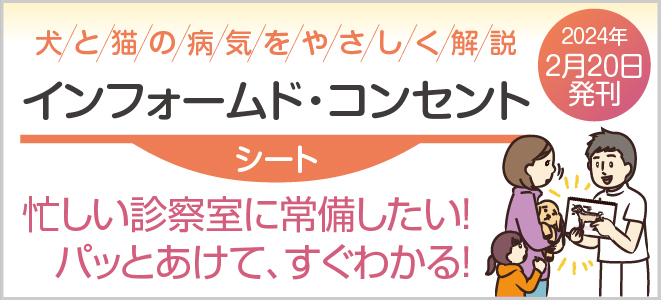各分野のトップランナーが、どのように学んできたのか。
そして、どのように学びを臨床に活かしているのか。
「明日の獣医療を創る」は、すべての臨床獣医師に捧げるインタビューシリーズ。
第16回は伊丹貴晴先生です。

麻酔がもつ魅力
―伊丹先生にとっての麻酔学、麻酔科の魅力を教えてください。
動物に麻酔をかけると、教科書に書いてあることと同じ反応が返ってきます。つまり、麻酔学は突き詰めたデータ通りの結果が返ってくる学問で、これが面白いんだと思います。師事した山下和人先生(酪農学園大学)はデータを重んじる診療体勢をつくられていて、それにならって私も1症例1症例のさまざまなデータをまとめ、統計学的に解析し、ケースごとのベストな麻酔方法を探っています。経験や感覚に頼るのではなく、データに裏付けられたEvidence Based Medicineが実践できる、そこが麻酔学の魅力です。
また、今後の獣医療の考え方にもなる「集学的個別化診療」が、率先して行えることも魅力の一つではないかと思います。例えば、心臓病のある患者に不妊・去勢手術を行う場合、使ってはいけない麻酔薬というものがあります。単にこの麻酔薬を「除外して手術をすればよい」というだけではなく、その他の麻酔薬を心臓病の患者にも適用し記録を続けることで、統計学的にベターな薬の選択が可能になる、ということです。これを一つ一つ積み重ねていき、A薬は血管収縮作用が出る、B薬は徐脈作用が出る、C薬はこれらの作用がないので、「この症例にはこういう理由でC薬を使うのがベストですよ」と判断できるようになります。また、新しい薬剤が出るたびに組み合わせは変わっていきます。一概に「心臓病の犬にはこの薬」で済ませるのではなく、集学化された知識を個別の疾患に合わせる形で臨床に積極的にアウトプットできるのが今の麻酔学です。Evidence Based Medicineを実践できる知識と技術は重要ですが、今の立場ではEvidence(=科学論文)を創ることが何よりの目標です。
もう一つ、麻酔科は治療のベクトルが他の診療科と異なることも興味深いところだと思います。外科治療や内科治療は生命活動を高めるために行います。でも、麻酔科は生命活動を止める方向にベクトルが向かい、死に近い状態にもっていきながらギリギリのところで生命を維持する。違う目的の複数の薬剤を組み合わせたり、モニタリングする能力が問われたりと、他の診療科では味わえない醍醐味があるのが麻酔科ではないでしょうか。
―2015年における世界獣医麻酔会議の日本開催、また麻酔ブートキャンプの活況をみると、麻酔への興味が獣医師の間で高まっていることが伺えます。獣医麻酔を巡る最近の状況、またトピックがあれば教えてください。

近年、麻酔学では「マルチモーダル鎮痛」という考え方が主流になっています。これは「複数の麻酔薬を効率よく織り混ぜて使う」という方法です。1つの薬剤を大量に使うと、吐き気や徐脈などの副作用が目立つようになります。でも、同じ鎮痛効果が得られるように2つ以上の薬剤を混ぜれば、それぞれの投与量を抑えることができるため、副作用も和らげることができるという考え方です。マルチモーダル鎮痛は大学でも教え始めていますし、獣医師の国家試験にも出題されました。今は一昔前の乱暴な麻酔管理は少なくなっている印象がありますが、それでも経験則に頼る傾向はまだ根強く感じています。是非、自身の経験則と比べてもらって、より良い方法だと思われたら積極的に採用してほしいと期待しています。
トピックと言えば、局所麻酔への回帰ですね。フェンタニルやモルヒネといった麻酔薬は全身に作用してしまいますので、どうしても悪心が出たり、鎮静が深くなりすぎるといった副作用が出てきます。局所麻酔薬は、患部もしくはその支配領域に投与することで知覚神経を遮断することができます。さらに、モルヒネなどが「鎮痛薬」であるのに対し、局所麻酔薬は「無痛薬」であることもメリットとなるでしょう。
今まで局所麻酔があまり使用されなかったのは、手術の際に使用できない部位がたくさんあったからです。でも、今は超音波やCT、MRIなどの画像診断機器の発展、さらには3Dプリンターなどを使用することにより、神経の走行が細かくわかるようになりました。おかげで体のいたるところの神経が遮断できるようになったことが大きいです。
局所麻酔を使いこなすには解剖学の知識が必要ですし、セミナーやウェットラボなどに参加して基本的な技術を学ぶ必要はありますが、無痛なので手術した動物もすぐにご飯が食べられる、飼い主さんにも術後すぐに面会してもらえる、そして飼い主さんからも非常に喜ばれるのが最大のメリットかもしれません(笑)。