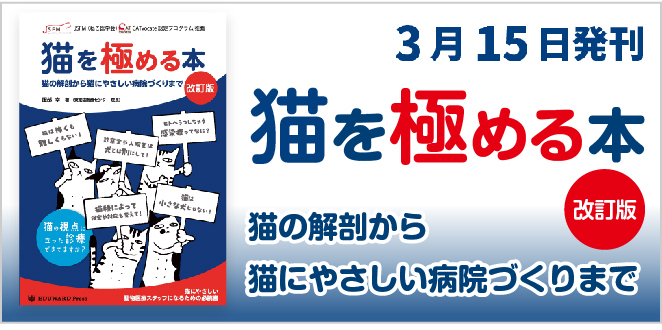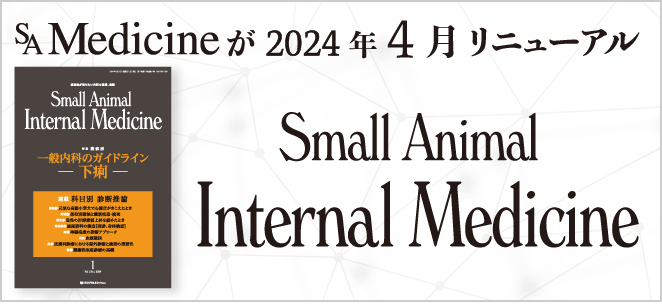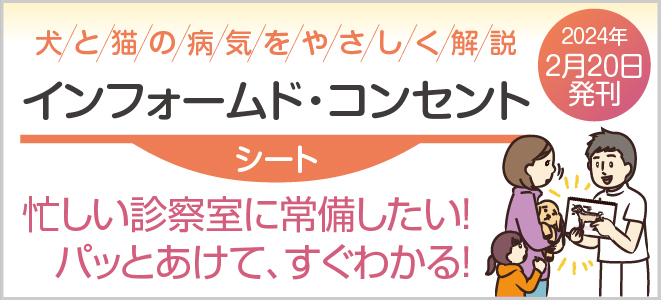各分野のトップランナーが、どのように学んできたのか。
そして、どのように学びを臨床に活かしているのか。
「明日の獣医療を創る」は、すべての臨床獣医師に捧げるインタビューシリーズ。
第12回は戸島篤史先生です。

日本人向けの教科書を作るのが目標
―戸島先生が画像診断の道に進まれた経緯を教えてください。
大学を出て、富山市の保健所に1年ほど勤務しましたが、やはり臨床がやりたいと思い、同じく市内の動物病院に勤めることにしました。その時、たまたま富山で行われていた宮林孝仁先生(獣医教育・先端技術研究所)の超音波実習を受講し、衝撃を受けたのが画像診断を志した始まりです。
当時はまだ1~2年の臨床経験しかなく、わからないことばかりの中、何がわからないのかをつきつめていくと結局は“画像診断がわからない”ということに、この講演を通して気付きました。画像診断がわかるようになれば、診断がスムーズになり、たくさんの動物を助けることができるようになるのではないかと思いました。
そして何よりもその実習の3時間が、私にとっては非常に面白かったんです。その場ですぐに宮林先生に「画像診断の勉強をさせてください」とお願いし、翌年、獣医教育・先端技術研究所に勤め始めました。そこで3年ほど、画像診断とティーチング法を学び、今の勤務先に勤めることになりました。
―画像診断を“指導する側”になって、見えてきた課題等はありますか?
もちろん私の教育力はまだまだ宮林先生の足元にも及ばないのですが、「わからないことがわかるようになった」と評価いただく充実感や、先生方と知識を共有できる喜びには計り知れないものを感じています。反面、画像診断の上達には「感覚」「慣れ」「経験」といった言葉が付きまといがちです。私はこれらの言葉が嫌いで…(笑)これらの言葉を言ってしまうと、そこで教育は終わってしまうんですよね。もう少しわかりやすくならないか?会得しやすくならないか?といつも意識し、“今出来るようになる”メソッドや方法論を臨床の視点から作り上げたいな、と思っています。
―日本小動物医療センターのホームページにて、戸島先生は「日本人の獣医師として日本人向けの教科書を書きたい」と発言されています。 そこにも通じるお話しですね。
そうですね。これらのメソッドや方法論を教科書というかたちにできれば、臨床の先生方が画像診断を会得するための一助になるのかもしれません。イメージとしては私が今セミナー等で講演しているような、疾患からではなく症状や画像所見から考える内容で構成した、臨床でよく診る疾患の画像診断方法を記載したいですね。大学で学んだ知識をフル活用できる、逆引き事典のようなものが理想です。
―出版社として放っておけない言葉です(笑)詳しく教えてください。
国内で臨床的に一番診る病気、例えば吐いている犬であれば急性胃腸炎だと思いますが、そもそもその急性胃腸炎を診断する方法が書いている本がないんです。よく診る疾患と稀な疾患を並列に書いているのが教科書の常で、臨床の観点からは本当に必要な情報は書いていなかったり、少なかったり、強調されていなかったりで、臨床をやっている人間からすると非常にわかりにくくて嫌だなと。また同じ疾患でも「フレンチ・ブルドッグだったらこうだよね」とか「猫ならこうだよね」といった犬種別,品種別の情報も網羅できると、臨床的には使いやすくなると思います。極論に響くかもしれませんが、100%ではなくとも、80%の診断確度を提供するものが、今臨床には求められていると思います。
―今後、画像診断をどのように発展させていきたいと考えていますか?

例えば画像診断でいくら肺がんだと思っても、病理検査をしてからでないと確定診断ができません。でも、実際にはなかなかできないですよ、組織生検なんて。検査のためだけに開胸・開腹するのは、飼い主さんも嫌なはずですし、動物にも負担がかかります。飼い主さんや動物のためにも、私は画像診断の優位性が少しでも高くなればと考えています。
幸い今は二次診療の現場にいるため、画像診断を行った症例の確定診断から治療までを見届けることで「診断の答合わせ」ができます。
さらには優秀な同僚たちからの意見や診療上の問題点の抽出も、以降の画像診断の参考にすることができます。加えて、数は力なりではないですが、診断書を書かないものも含めると、私は年間約5000例の画像診断を行っています。これは私の何ものにも代えがたい財産です。
こうして集めた画像診断の知識やデータを、少しでも臨床に還元することができたら本望に思います。