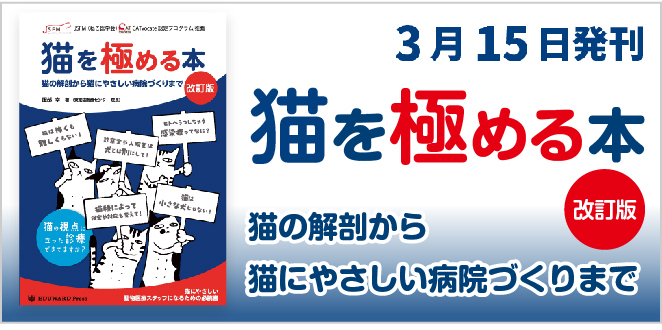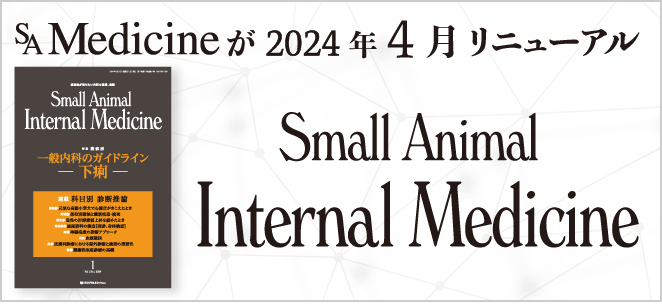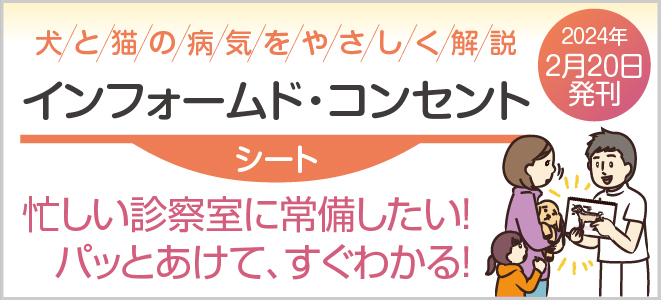各分野のトップランナーが、どのように学んできたのか。
そして、どのように学びを臨床に活かしているのか。
「明日の獣医療を創る」は、すべての臨床獣医師に捧げるインタビューシリーズ。
第10回は長谷川大輔先生です。

人生のターニングポイントとなる論文との出会い
本インタビューは、長谷川先生の研究室にて行われました。柔和な笑顔で取材班を迎え入れてくれた長谷川先生の背後では、ライムスターからパブリック・エナミー、最新からクラシックまで、縦横無尽にヒップホップが流れていました。
―ヒップホップを聞かれるんですね。
はい、昔あったテレビ番組の企画「ダンス甲子園」に影響を受けて、聞きはじめるようになりました。初めはダンスにハマり、その流れからDJに興味をもち、最終的にはプロのDJに弟子入りして腕を磨いていました(笑)。ハマリにハマって、収集した12インチレコードの数は4000枚を超えるほどです(結婚・引っ越しを機に95%は処分してしまいましたが…涙)。一時、獣医の道かDJの道かを天秤にかけました。DJの師匠が「せっかく獣医の大学に入ったんだから、ちゃんと獣医師になりなよ」といわれて獣医になりました。
―そんな葛藤を経て、長谷川先生が脳神経外科を志したのはどういう理由からでしょうか?
学生の頃から特に興味をもっていた分野が「脳」と「心臓」です。また、誰も手を出していない分野を研究したいとも考えていたため、権威と呼ばれる先生方がすでにいらっしゃった心臓外科ではなく、専門にしている先生がほぼいない脳神経外科の道へと進むことにしました。
しかし、そう決めたのはよいものの、師事できる脳外科の専門家がいないわけです。そこで、同じ大学で椎間板の研究をしていた原 康先生の研究室へと進みました。原先生は元々整形外科が専門のため、私も整形外科班に所属する一方、面白そうな脳神経外科の海外論文をこまめにみつけてきては「翻訳したい!」と提案したり、卒業論文のテーマを「下垂体切除術」にしたりと、自分が興味のある脳神経外科の分野へと近づくための努力を続けました。
下垂体切除術については満足のいく結果を残しつつも、本来、下垂体は内分泌器官のため、その研究となると内分泌病理や分子生物学的研究になってしまい、脳外科とは少し違ってきます。大学院は神経病と画像診断を専門にされている織間博光先生の下へ進学しましたが、今後自分はどのような研究をしていけばよいのかと、模索する日々が続きました。
― その後、神経系の研究をはじめられたわけですが、そのターニングポイントはどこだったのでしょうか?
当時、旭川医科大学の脳神経外科にいらっしゃった田中達也先生と橋詰清隆先生らによる「難治性てんかんの外科治療:実験てんかんからのアプローチ」という論文との出会いです。この論文の内容は、「(MRIを使わずに)脳図譜と脳定位装置を使って猫の実験てんかんモデルをつくり、その焦点を脳外科手術で切除する」というものです。「大学にもある脳定位装置でこれだけのことができる」と知った私は目から鱗が落ちる思いでした。てんかんは、神経病で一番多くみられる脳疾患です。日獣大の付属病院にもたくさんの患者が来ているのにもかかわらず、当時は外科で治すという意識がありませんでした。つまり、誰も手がけていない脳神経外科の研究テーマがそこにあったのです。
もちろん、田中・橋詰両先生とは面識がありません。若気の至りで「ぜひ獣医学の分野でこの研究をしたいので、実験方法を教えてください」というメールを送りつけた私に、先生方は快諾のお返事をくださいました。私は、織間博光先生の承諾と援助を得て、さっそく旭川へと飛びたち、両先生にさまざまな知見を教えてもらうことができました。
このように、多くの先生方からの助力をいただいたおかげで、私はてんかんに関するさまざまな論文を発表でき、てんかんの研究をライフワークにするようになりました。