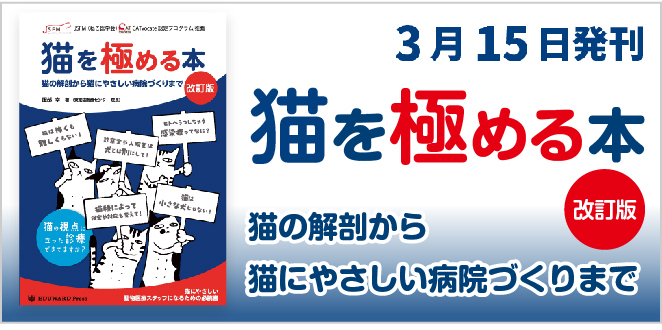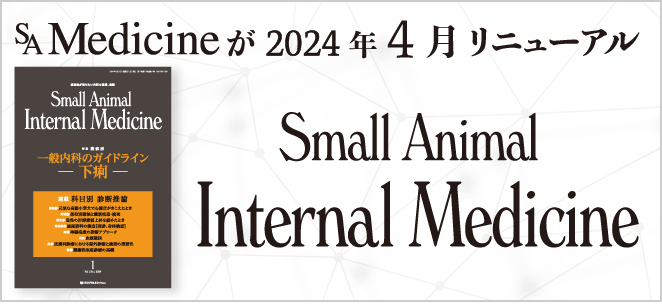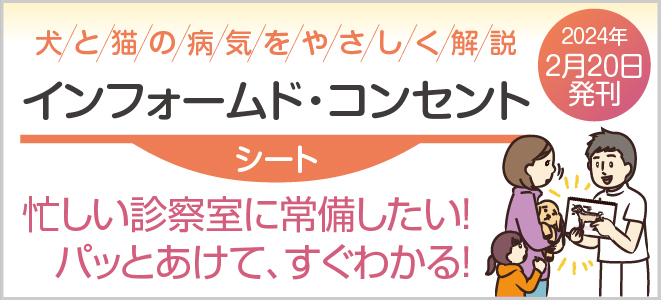これからの獣医療はどうなっていくのか。
そして、獣医師は今後どのように学んでいくべきか。
インタビューシリーズ「獣医療のミライ」では、
各分野で活躍する新進気鋭のスペシャリストたちに、
研究や臨床から得た経験をもとにした
未来へのビジョンや見解を語っていただきます。
第8回はとがさき動物病院 院長、日本小動物外科専門医の灰井康佑先生です。

好きこそものの上手なれ 臨床外科医への道へ、一直線
―まずは、灰井先生が獣医師を目指された経緯からお教えください。
私は千葉県の田舎のほうの出身なんですが、子供のころからクワガタを捕まえに行ったり、動物と遊んだりというのがすごく好きで、自然に獣医師の道を選んだような気がしています。高校時代を振り返っても、数学などの一般的な科目は苦手だったのに、生物だけはなぜか得意でした。大学受験には苦戦しましたが、入学してからの勉強はほぼすべてが興味ある分野だったからなのか、苦にならなかったんです(笑)。
―まさしく「好きこそものの上手なれ」ですね(笑)。外科学研究室を選ばれたきっかけは?
獣医師には公務員や会社員などさまざまな働き方があると思うのですが、当時の私にとっての獣医師のイメージは「小動物を診療する町の獣医師」だけ。目指す道に少しでも早く近づこうと、大学2年目から毎年、夏休みなどに地元の動物病院でお手伝いをさせてもらっていました。その病院の先生が、「動物病院で働くなら外科ができないとね。ヘルニアの手術ぐらいはできたほうがいいよ」と仰っていたのが印象的で……。それで、素直に「そうか。ヘルニアの手術ができなければいけないのか」と、意識下に植え付けられちゃったんですかね(笑)。その一言が、外科を選ぶ後押しになりました。
―実際に外科学研究室に入って、いかがでしたか?
最初は緊張の連続でした(笑)。学生だった我々が手術のサポートに入る際も、まずは指導教官の前で、使う器具と出す順番、術式をすべて口頭でプレゼンできて初めて、器具助手に入れるという感じで……。その内容も、誰かが手取り足取り教えてくれるわけじゃないですから。今、振り返って思えば、自分で学ぶ姿勢そのものを教えていただいたのだと思っています。