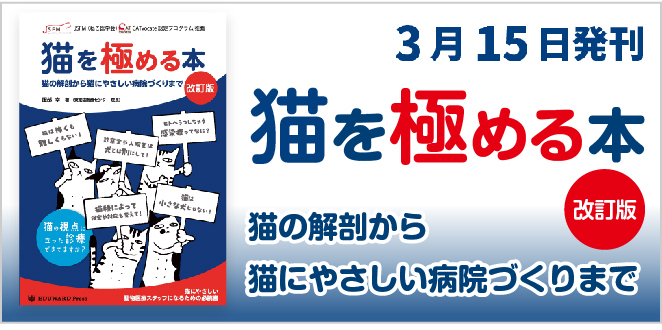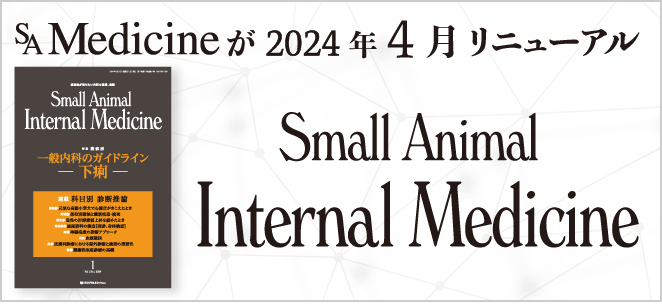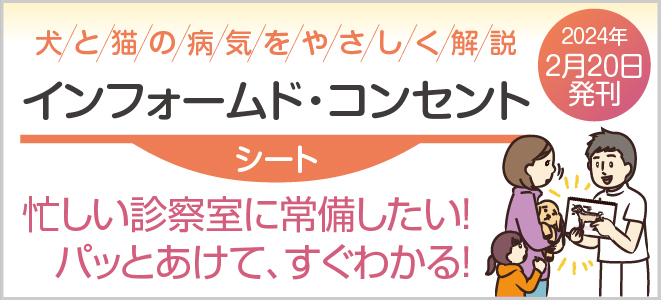これからの獣医療はどうなっていくのか。
そして、獣医師は今後どのように学んでいくべきか。
インタビューシリーズ「獣医療のミライ」では、
各分野で活躍する新進気鋭のスペシャリストたちに、
研究や臨床から得た経験をもとにした
未来へのビジョンや見解を語っていただきます。
第6回は東京農工大学大学院 農学研究院動物生命科学部門 准教授、農学部共同獣医学科 博士(獣医学)、アジア獣医内科学専門医(内科)の大森啓太郎先生です。
「尖ったナイフ」だった学生時代と臨床への興味
―大森先生が獣医療の道に進まれたきっかけを教えてください。
中学、高校の頃は獣医師になろうという気持ちは全くなかったのですが、進路の方向性として漠然と考えていたのは理系でした。特に生物学に興味があり、消去法的に獣医学科を選んだんだと思います。亀や水生生物がわりと好きだったのもありますし、それに実は私、気持ち悪い生き物に心惹かれる癖(へき)があって(笑)。大学でも寄生虫を研究対象とする医動物学研究室に所属。学部生時代の休み時間は寄生虫関連の書籍を図書館で読みあさっていました。今思えば、ちょっと変わった学生でしたね(笑)。また、自省を込めて振り返れば、自分の正しさだけを鋭く人に突きつける「尖ったナイフ」のような学生だったとも思います。だから、指導教官も扱いに困ったのかもしれません。大学5年生のある日、水戸市で開業されている同級生の方の病院に1カ月間、実習に行くことを勧められたんです。
―実習生活がその後の進路に影響したのでしょうか。
はい。一次診療のリアルな現場に触れられたのは大きな刺激でした。例えば、院長先生は痒みを主訴に来院した犬が脱毛した皮膚を舐め続ける様子をみて、「ホットスポットだね」とすぐ判断し、ステロイドを打つ。次の日の再診ではかなりよくなって、飼い主さんが喜ぶというような……。「こうやって自分が学んだ知識が社会に役立つんだ」と衝撃を受け、臨床に進みたいと考えるようになりました。